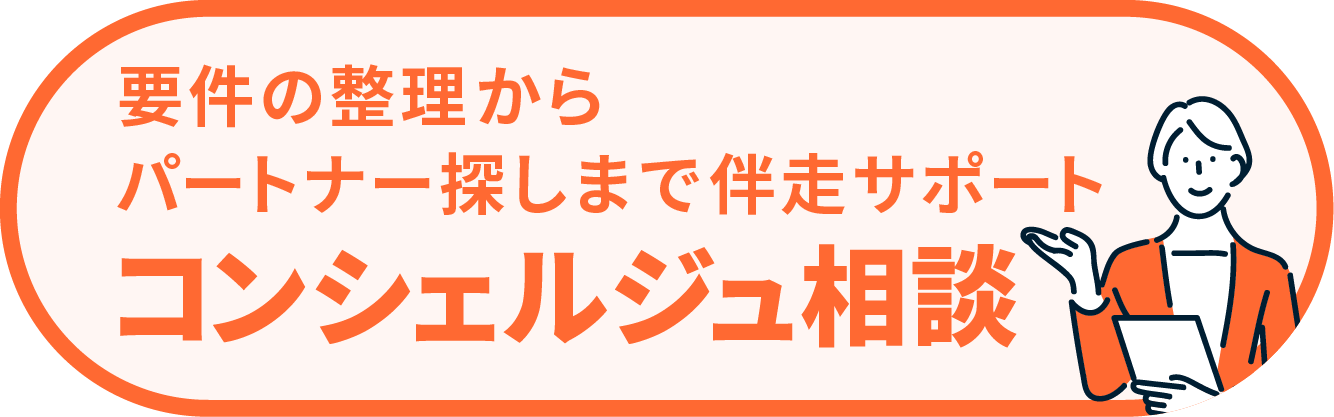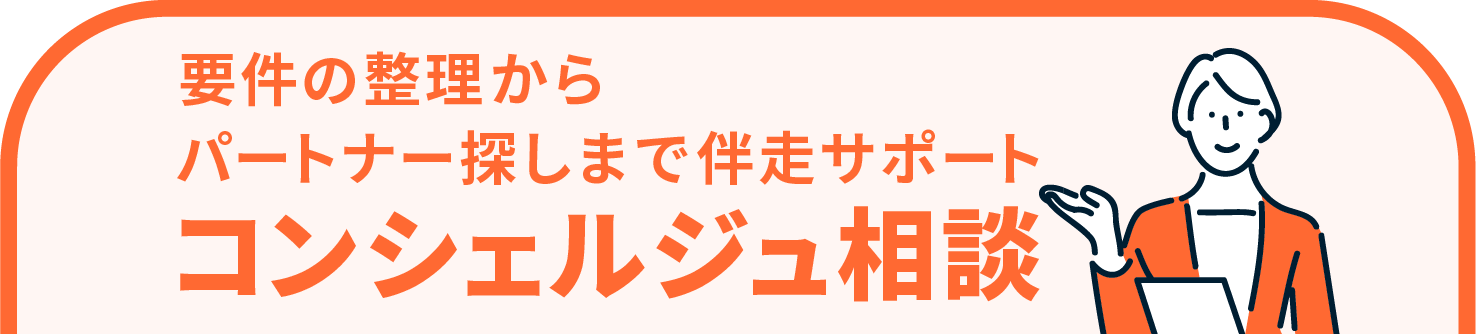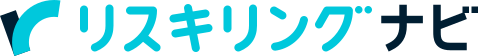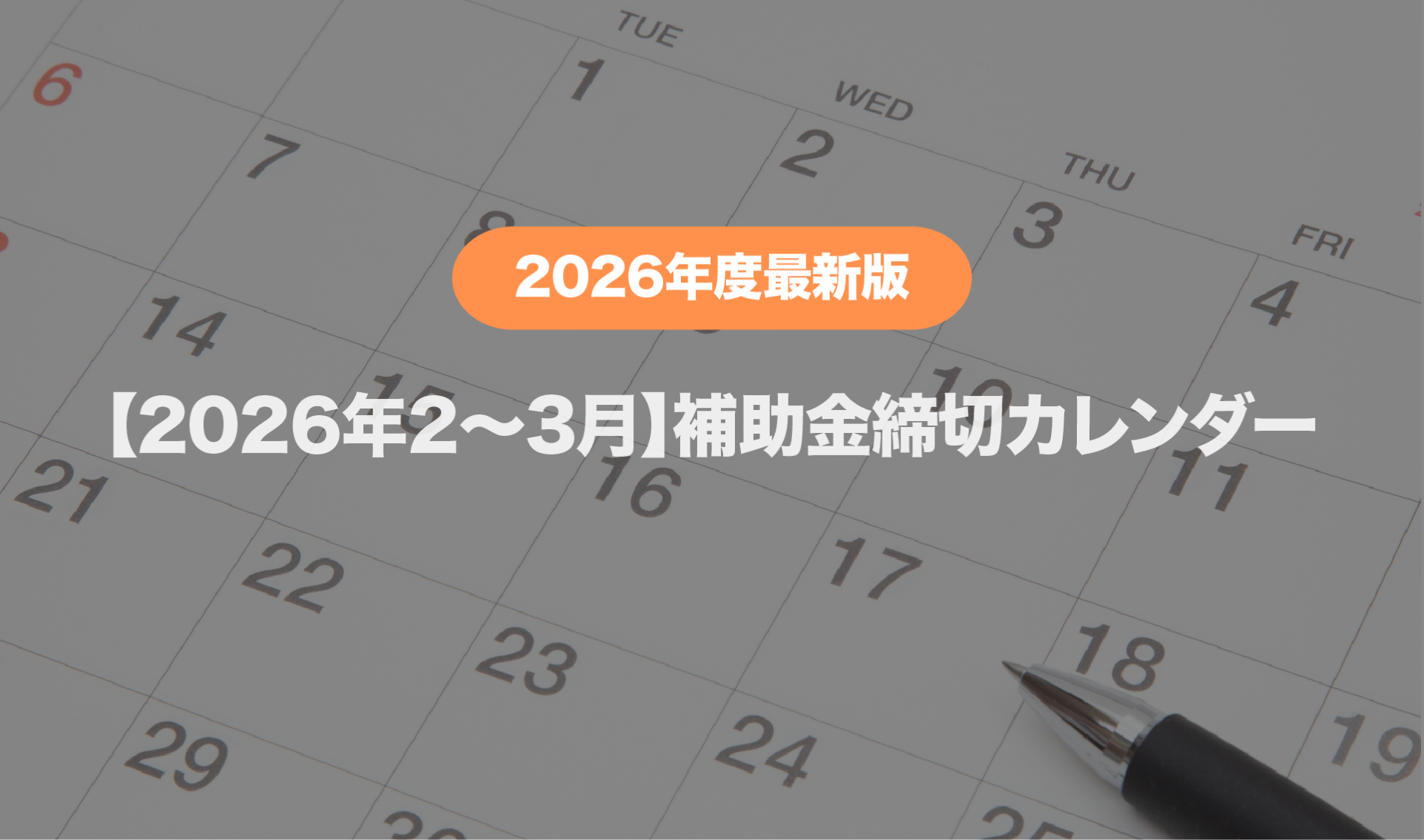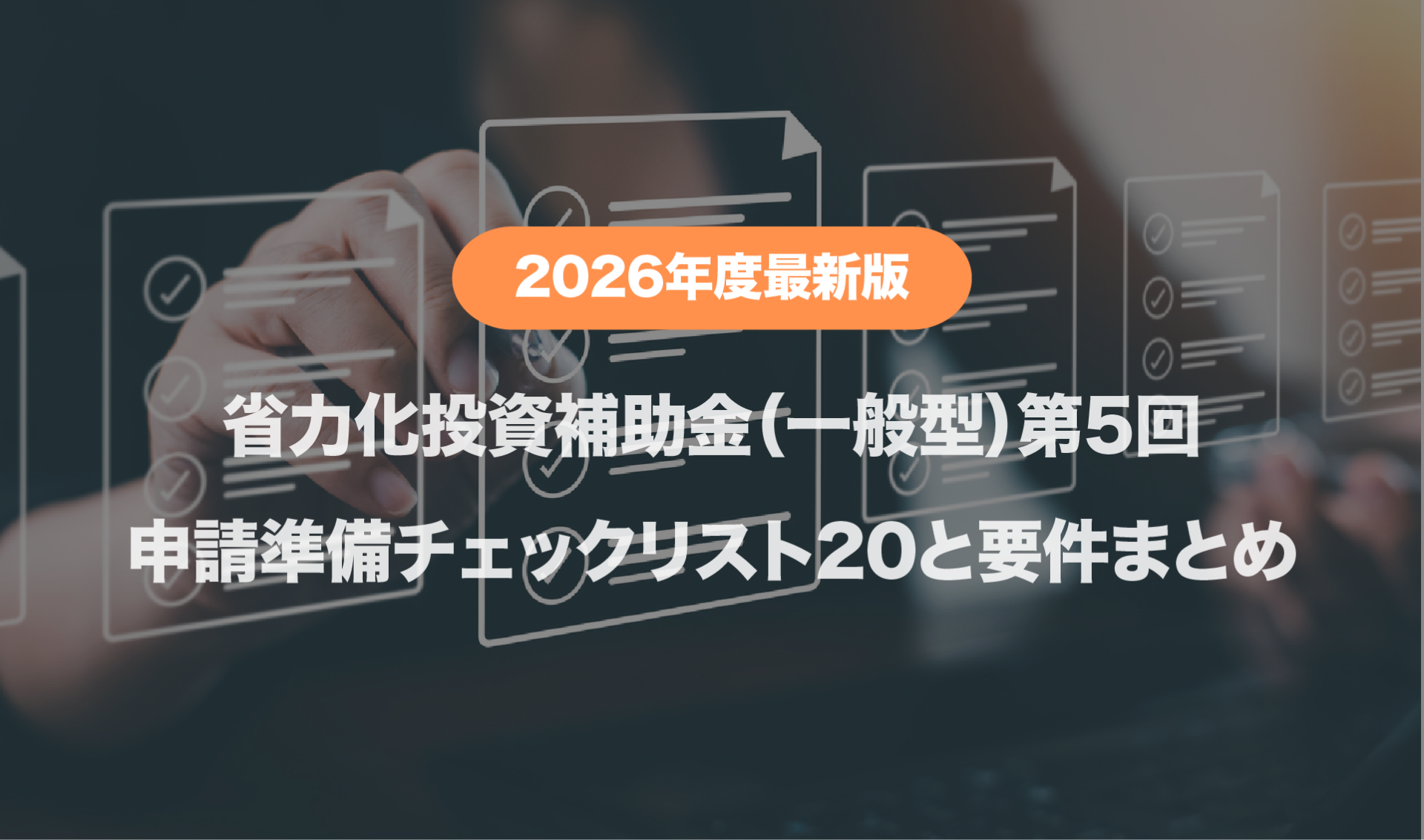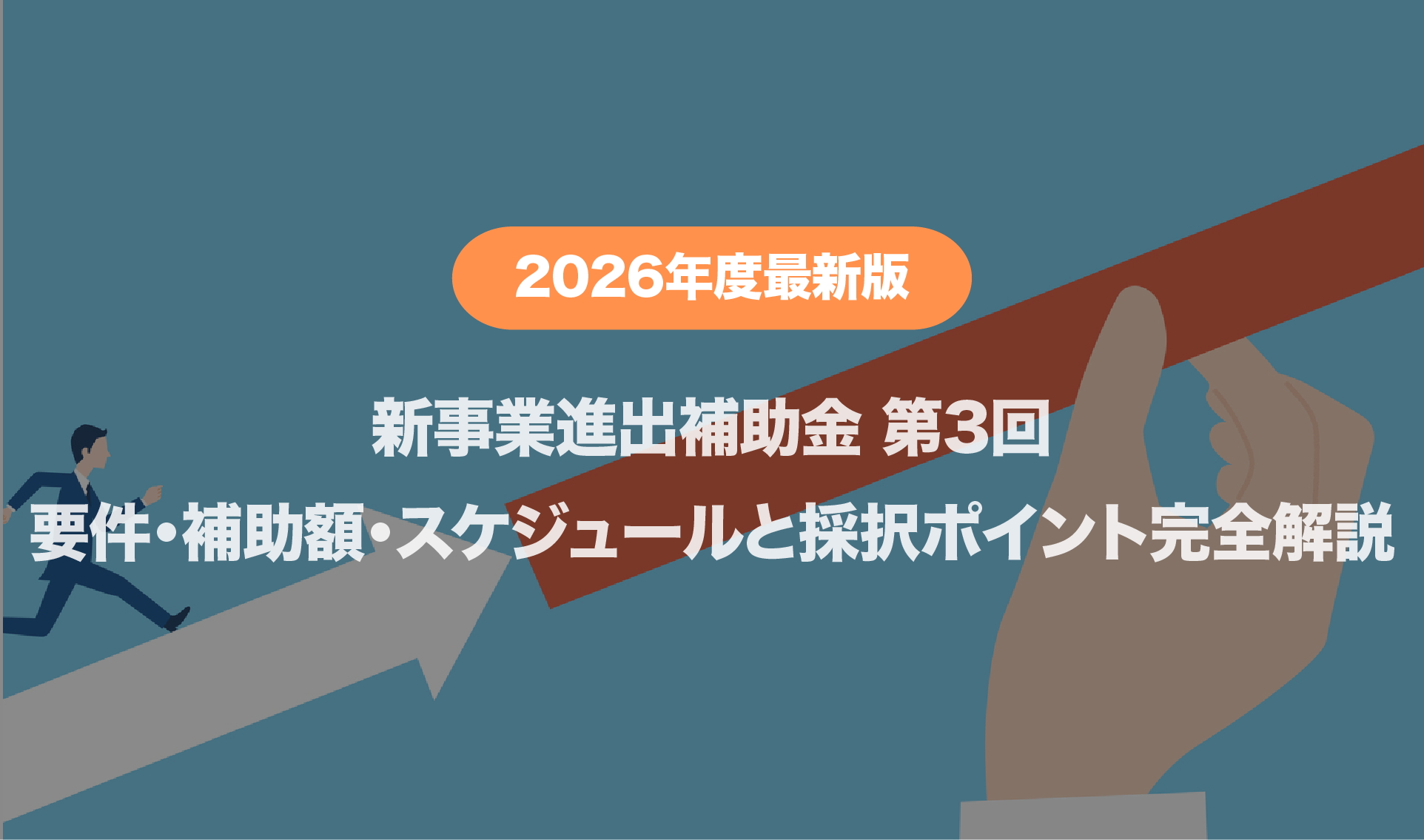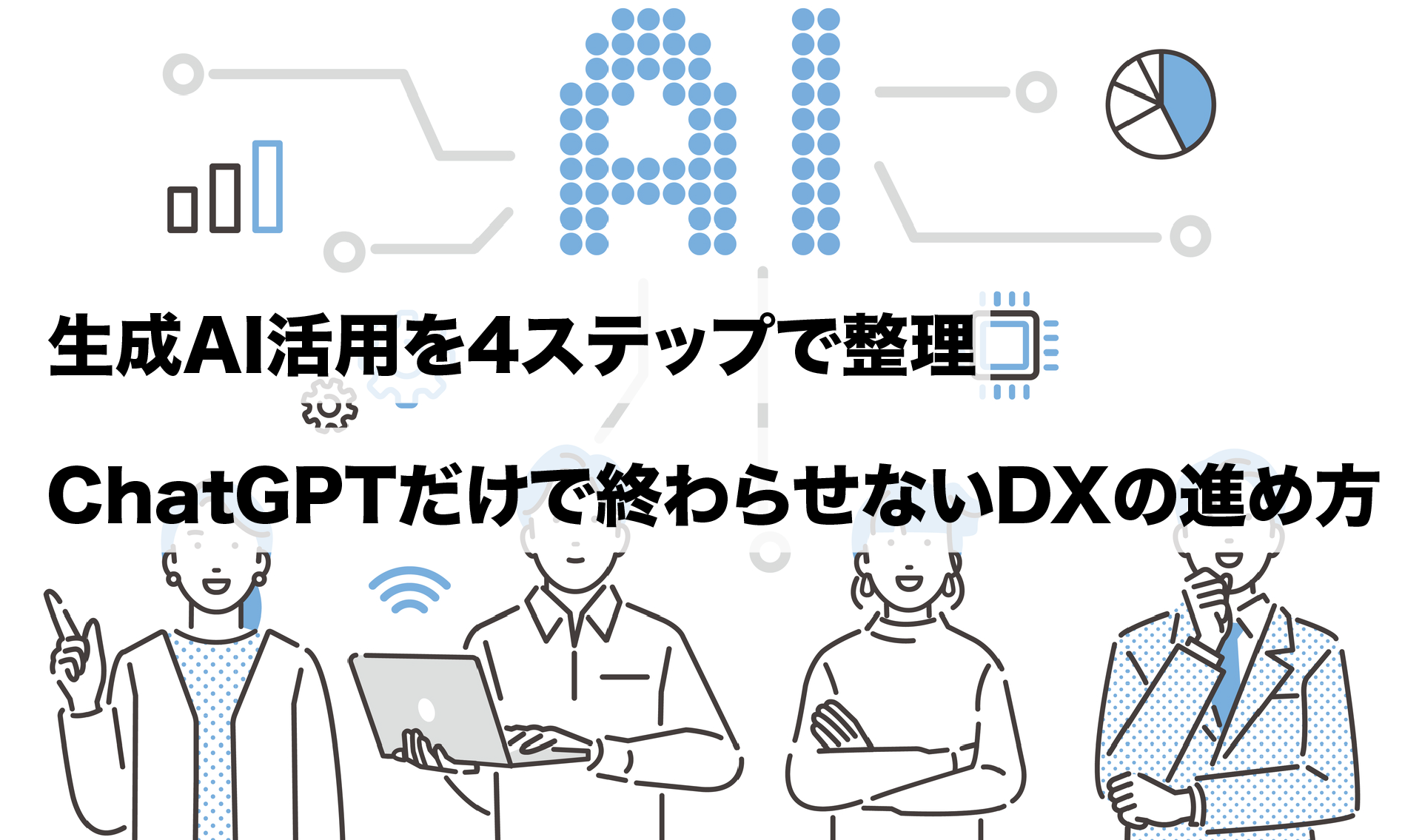【2025年版】人材開発支援助成金を完全解説|最新改定・コース別の違い・助成額・申請方法まとめ
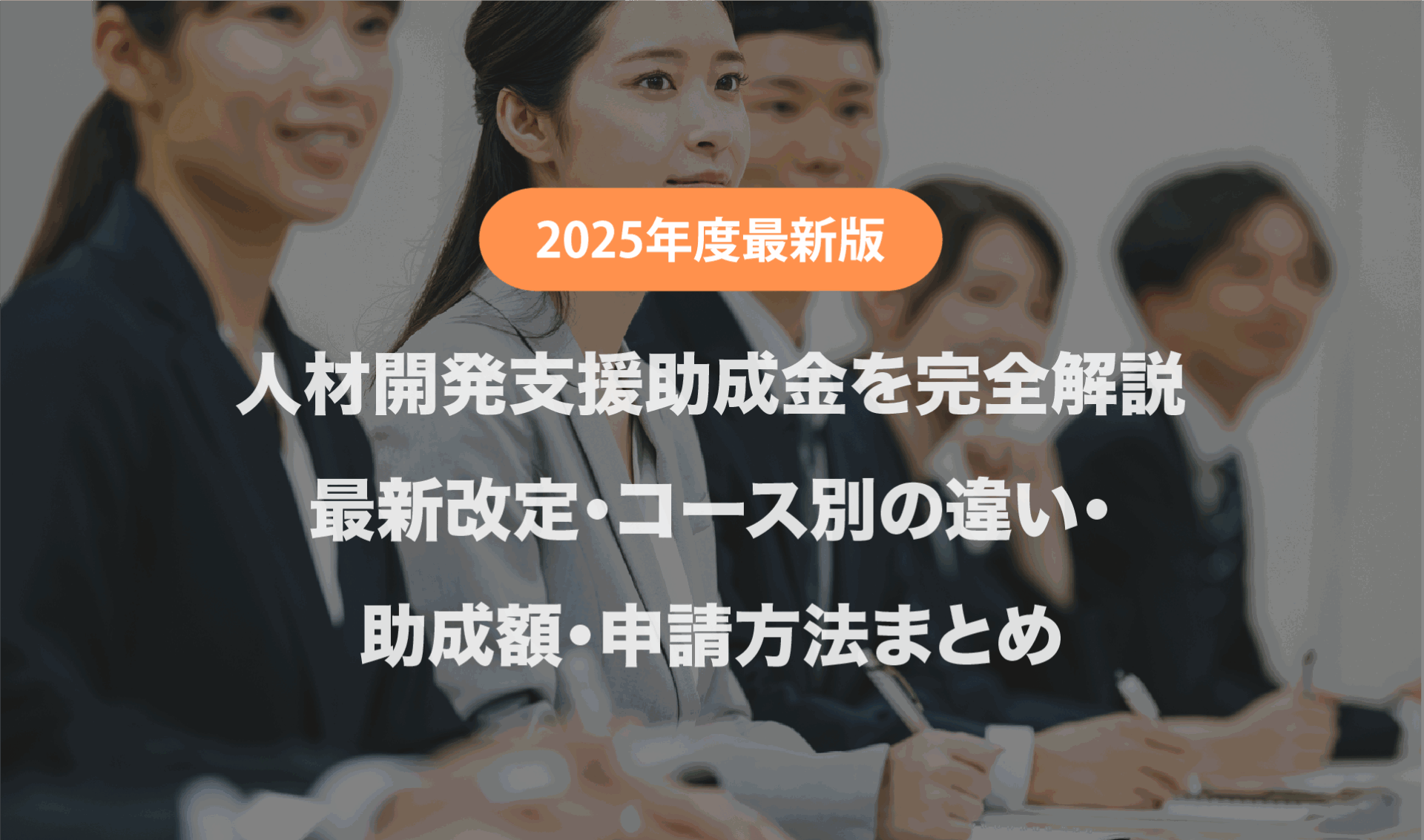
目次
人材開発支援助成金とは?制度の概要と目的
人材開発支援助成金は、企業が従業員に対して職務に関連する教育訓練を実施した際に、その訓練にかかる経費や、訓練期間中に支払う賃金の一部を国が助成する制度です。
特に中小企業にとっては、社員のスキルアップや定着率の向上といった人材投資にかかる負担を軽減できる、有効な支援策といえます。
令和7年度(2025年4月)の制度改正では、賃金助成額の引き上げや非正規雇用者に対する支援強化、申請手続きの簡素化などが盛り込まれ、より実務的に使いやすい制度へと改善されました。
【改定ポイント】2025年(令和7年)施行の主な変更点
1. 賃金助成額の引き上げ
「人材育成支援コース」における中小企業向けの賃金助成については、以下のとおり改正が行われました。
| 区分 | 改定前 | 改定後(2025年〜) |
|---|---|---|
| 通常 | 760円/時間 | 800円/時間 |
| 賃上げ要件達成時 | 960円/時間 | 1,000円/時間 |
他のコース(人への投資促進、リスキリング支援など)でも賃金助成は原則1,000円に統一されています。
2. 非正規社員(パート・有期雇用)への支援強化
⚫︎有期実習型訓練では、訓練終了後に正社員へ転換することが助成の要件となっています。
⚫︎正社員化が実現した場合、経費助成率は最大で100%となるケースもあります。
⚫︎一定の条件を満たす場合には、正社員への転換が実現しなかった場合でも、助成対象となる例外的な扱いが認められることがあります。
※また、一部の解説では、経費助成率が最大75%程度に引き上げられたとする内容も確認されていますが、実際の適用要件は最新の制度資料をもとに確認する必要があります。
3. 書類審査・提出手続きが簡素化
⚫︎2025年度の制度改正により、事前審査が廃止され、計画届を提出すればそのまま受理される仕組みに変わりました。助成金の支給可否については、訓練終了後にまとめて審査されます。
⚫︎書類の添付が一部不要となったほか、雇用関係助成金ポータルによる電子申請にも対応しており、企業の事務負担は大幅に軽減されています。
4. オンライン研修・在宅訓練の対象拡大
⚫︎テレワークやリモート研修に関する制度要件は、近年の制度改正により一部緩和されています。
⚫︎そのため、研修時にリモートワーク用の就業規則を提出しなくてもよいケースもあります。
⚫︎eラーニングなどを利用する場合には、LMS(学習管理システム)による受講状況の把握や記録の保存など、別途定められた要件を満たす必要があります。
【コース別】助成内容と条件の違い(令和7年度)
各コースの訓練対象・助成率・上限金額・賃金助成額は以下の通りです。
| コース名 | 対象訓練 | 経費助成率 | 賃金助成 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 人材育成支援コース | OFF-JT/OJT併用/有期訓練 | 70%(賃上げ要件時85%) | 800円(同1,000円) | 年間上限1,000万円程度 |
| 教育訓練休暇付与 | 有給訓練休暇制度導入 | 定額(例:30万円) | 1日6,000円 | 上限日数あり |
| 人への投資促進コース | DX・成長分野訓練など | 45%(一部加算あり) | 1,000円 | 上限:2,500万円など |
| 事業展開リスキリング | 新分野進出に向けた訓練 | 最大75% | 1,000円 | 上限:年間1億円 |
| 建設労働者訓練 | 建設技能・認定訓練 | 一定割合 | 一部助成 | OJT訓練コースあり |
※2024年度より「障害者訓練」は人材開発支援助成金から除外され、別制度に移行しています。
対象企業と訓練の基本要件
⚫︎雇用保険適用事業所であること
⚫︎職業能力開発計画の策定と従業員への周知
⚫︎訓練内容が職務に関連し、10時間以上(OFF-JT)
⚫︎訓練費用は事業主が全額負担
⚫︎労務管理・法令順守(離職率、不正受給履歴なども審査対象)ます。
申請の流れ|5ステップで理解する手続き
1. 社内体制の整備
訓練対象者の選定や訓練方針の検討を行い、「職業能力開発推進者」を選任します。訓練の目的や計画内容は、社内で周知しておく必要があります。
2. 訓練計画届の提出
訓練の開始予定日の1か月以上前までに、「職業訓練実施計画届」を管轄の労働局に提出します(電子申請も可能)。2025年度以降は事前審査が廃止され、届出制に一本化されています。
3. 訓練の実施
計画に沿って訓練を実施します。受講者の出席記録やカリキュラムの進行状況を適切に記録し、OJTを含む場合は講師の指導内容や指導時間についての記録も求められます。
4. 支給申請
訓練終了後、原則として2か月以内に支給申請書類を提出します。不備があった場合や期限を過ぎた場合は、不支給となる可能性があるため注意が必要です。
5. 審査・助成金の支給
支給申請後、労働局での審査を経て、通常は2〜3か月程度で指定の口座に助成金が振り込まれます。申請の混雑状況や修正対応の有無によって、支給までの期間が延びることもあります。
助成額を最大化するためのポイント
1. 賃上げ要件を活用する
基本給を5%以上引き上げたり、資格手当などを新たに導入したりすることで、助成率や賃金助成額を上乗せすることが可能です。
2. 非正規雇用の正社員化とあわせて申請する
有期実習型訓練などを実施した後に正社員へ転換した場合、経費助成率が最大で100%まで引き上げられます。
3. 複数のコースを年間で戦略的に活用する
一人の従業員につき年間3回まで申請が可能です。スキルの段階的な向上を目的として、異なるコースを組み合わせることも検討できます。
4. 目的に応じて適切なコースを選ぶ
たとえば、DX関連の研修には「人への投資促進コース」、事業再構築を視野に入れた訓練には「事業展開等リスキリング支援コース」など、目的に応じたコース選定が助成の効果を最大化します。
5. 申請前に社労士など専門家のチェックを受ける
記載ミスや要件の見落としによる不支給を防ぐため、申請書類の作成段階から社労士や助成金に詳しい専門家のアドバイスを受けることが有効です。
不支給を避けるための注意点
⚫︎締切は厳守することが重要です
提出期限を1日でも過ぎると、原則として受理されません。
⚫︎書類の不備や証拠書類の不足には注意が必要です
申請書類に漏れがあったり、必要な証憑が不足していると、不支給の原因になります。
⚫︎計画と異なる訓練を実施する場合は、必ず変更届を提出しましょう
変更届を出さずに計画と異なる内容で訓練を行った場合、助成の対象外となる可能性があります。
⚫︎支払い構造に不正があると助成金は支給されません
例えば、外注費の一部を事業者が受け取る「キックバック」など、不適切な契約は重大な不支給理由になります。
⚫︎「必ずもらえる」といった根拠のない営業には注意が必要です
制度には細かな要件があり、誰でも必ず受給できるものではありません。過度なセールストークには慎重な対応が求められます。
⚫︎訓練後に離職者が多い場合は、審査上不利になることがあります
制度の目的は定着支援であり、訓練後すぐに退職者が多数出ると助成の趣旨に反すると見なされる可能性があります。
まとめ
人材開発支援助成金は、2025年の改定により、助成額の引き上げ・手続きの簡素化・非正規雇用支援の強化など、中小企業にとってさらに使いやすい制度へと進化しました。
自社の育成方針や経営課題に沿って、適切なコースを選び、制度の要件を正しく満たせば、大きな助成効果が得られます。
申請直前には、必ず厚生労働省の最新の公式パンフレットや支給要領をご確認ください。制度の詳細や最新の要件、必要書類の様式などが反映されています。
また、不明点や書類作成に不安がある場合は、社会保険労務士や助成金に詳しい専門家と連携して準備を進めることをおすすめします。
参考:厚生労働省による一次情報・公式リンク
人材開発支援助成金 総合ページ(制度全体・各コース案内・Q&A・様式)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
令和6〜7年度版 パンフレット・詳細資料(制度要件、10時間要件、手続フロー、上限額など)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001514280.pdf
雇用関係助成金ポータル(電子申請用)と GビズID の案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00060.html
人材開発支援助成金の活用は株式会社X-navi(クロスナビ)にご相談ください
「どのコースを選べばいいか分からない」
「計画届や支給申請の書き方に不安がある」
「申請しても不支給になるのでは?」
人材開発支援助成金の活用を検討されている中小企業様の中には、
そんなお悩みを抱える方も多くいらっしゃいます。
株式会社X-navi(クロスナビ)では、製造業・サービス業・IT企業など、幅広い業種における助成金申請の支援実績がございます。
人材開発支援助成金においては、「賃金助成を最大限活用する戦略設計」や「非正規雇用者の正社員化と連動させた申請」など、制度を活かしきるための具体的なご提案も可能です。
また、訓練計画の設計段階から、申請書類の作成、訓練の実施フォロー、支給申請、実績報告まで、経験豊富な専門スタッフが一貫してご支援いたします。
制度を単なる資金調達手段としてではなく、「人材戦略・組織強化の一環」として活用したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
パートナー企業