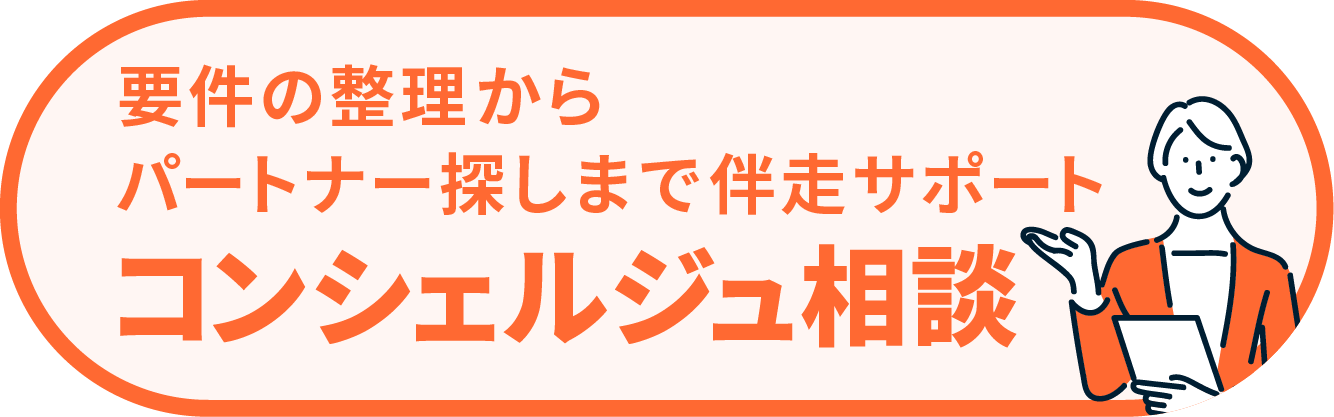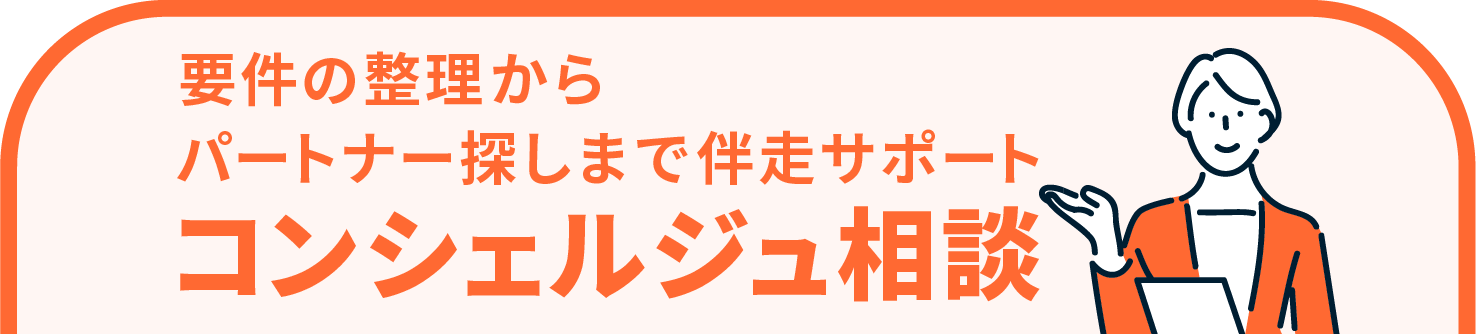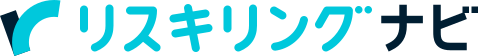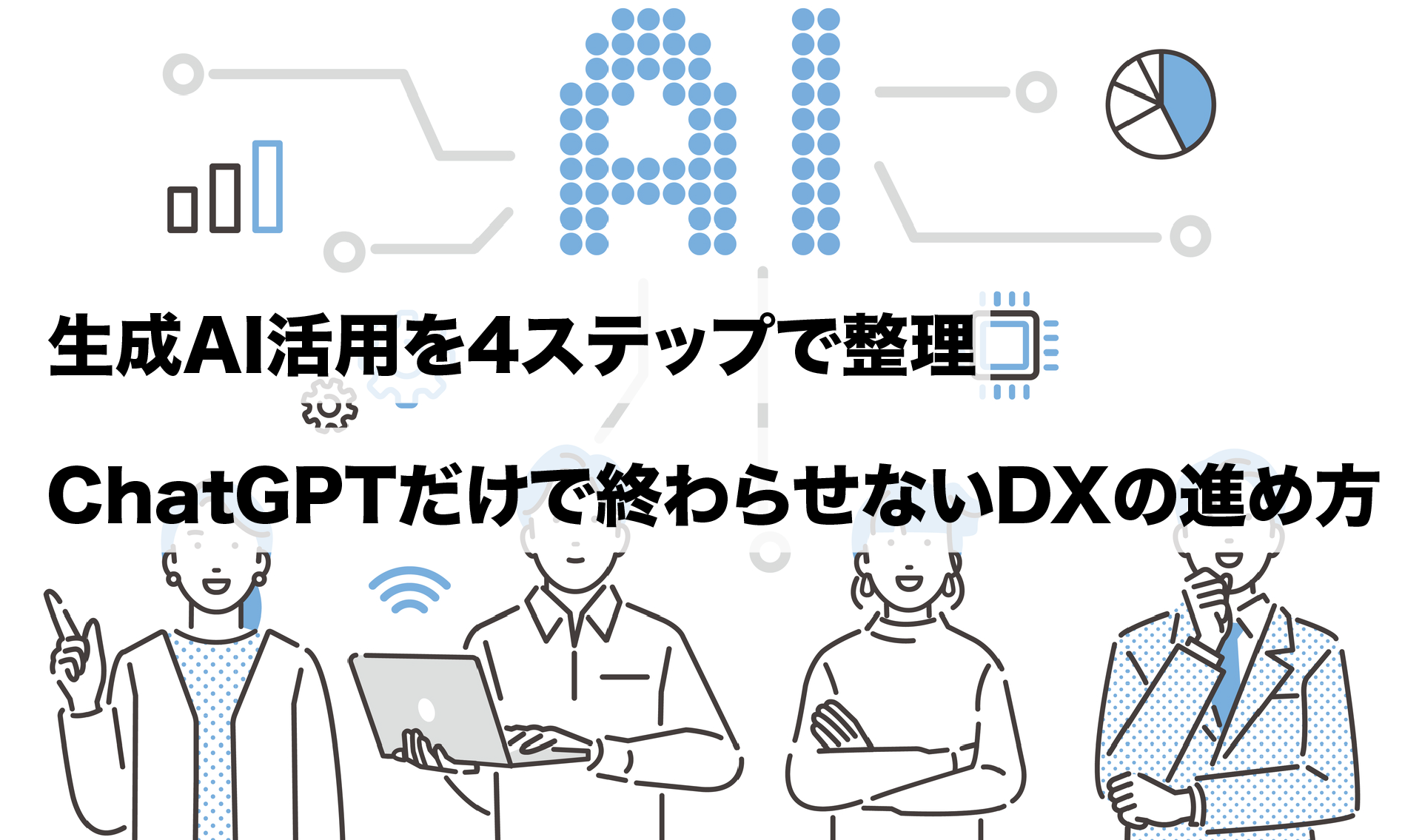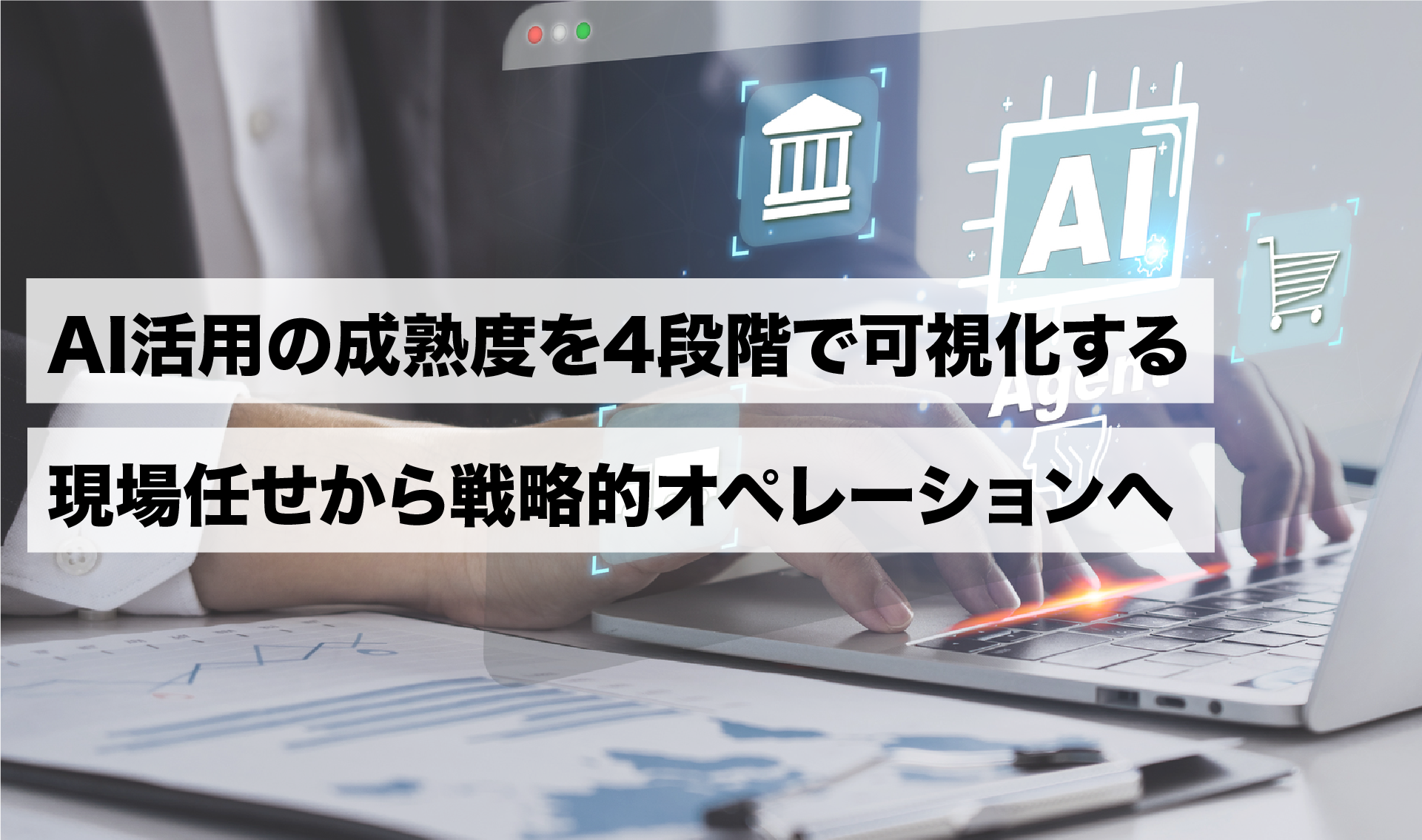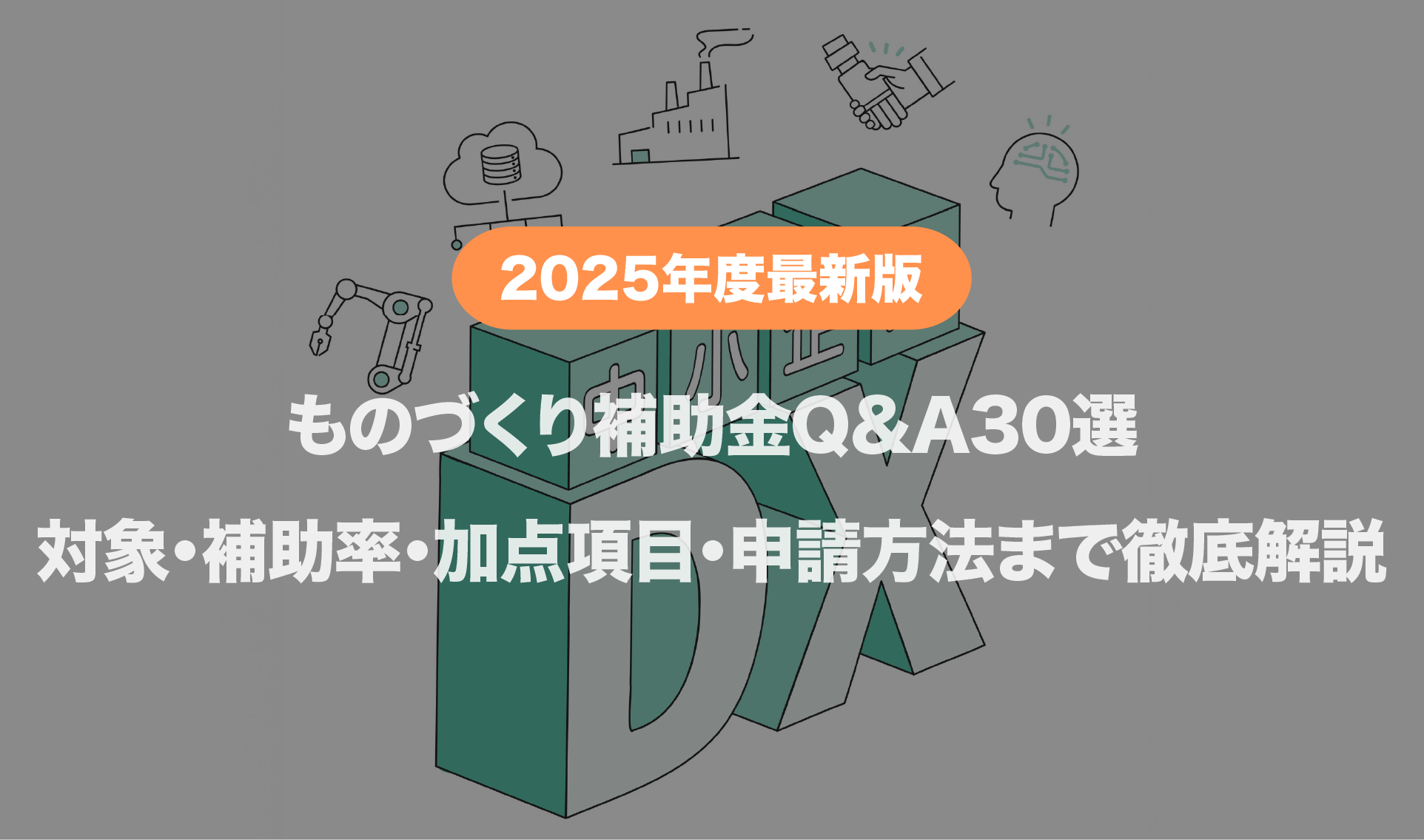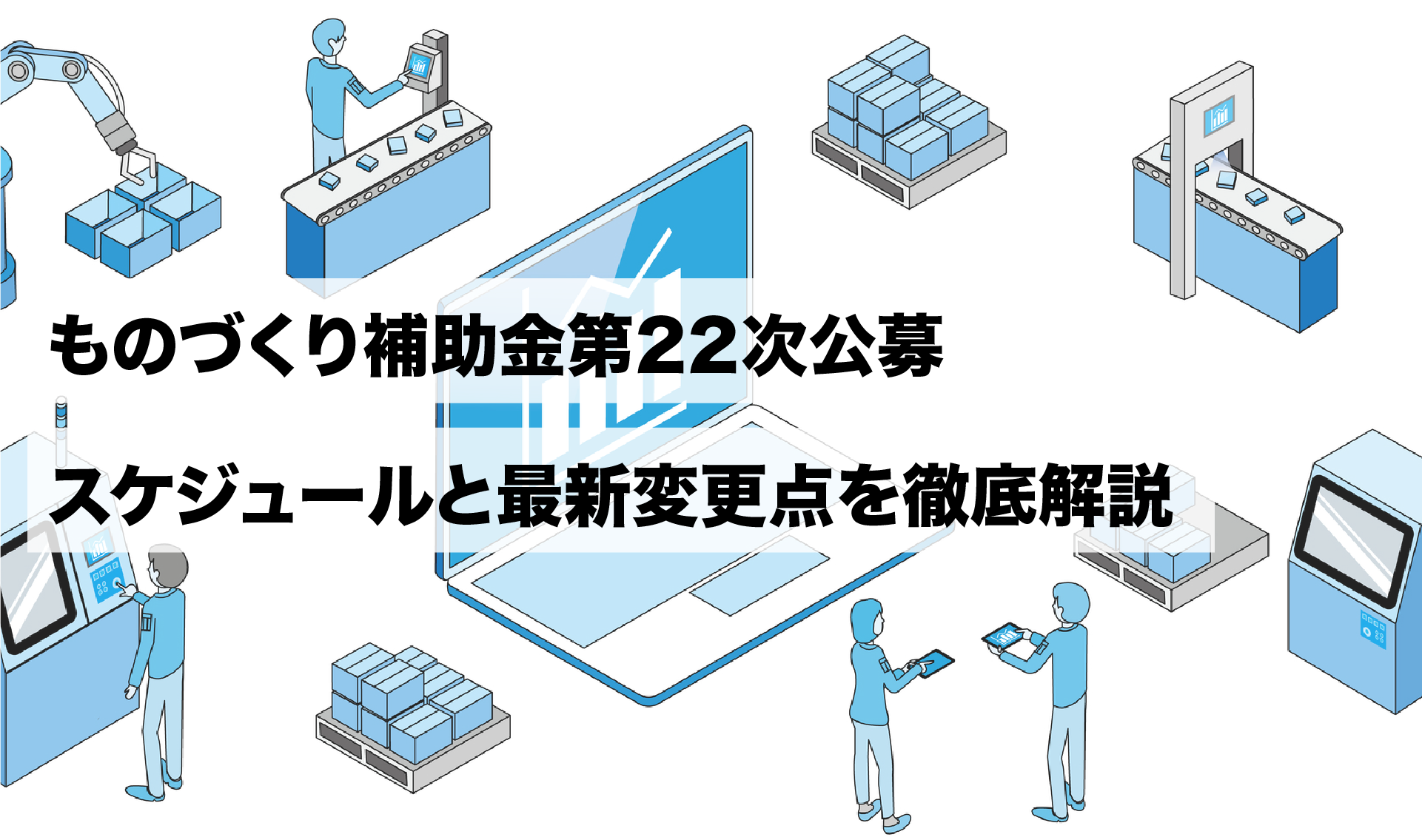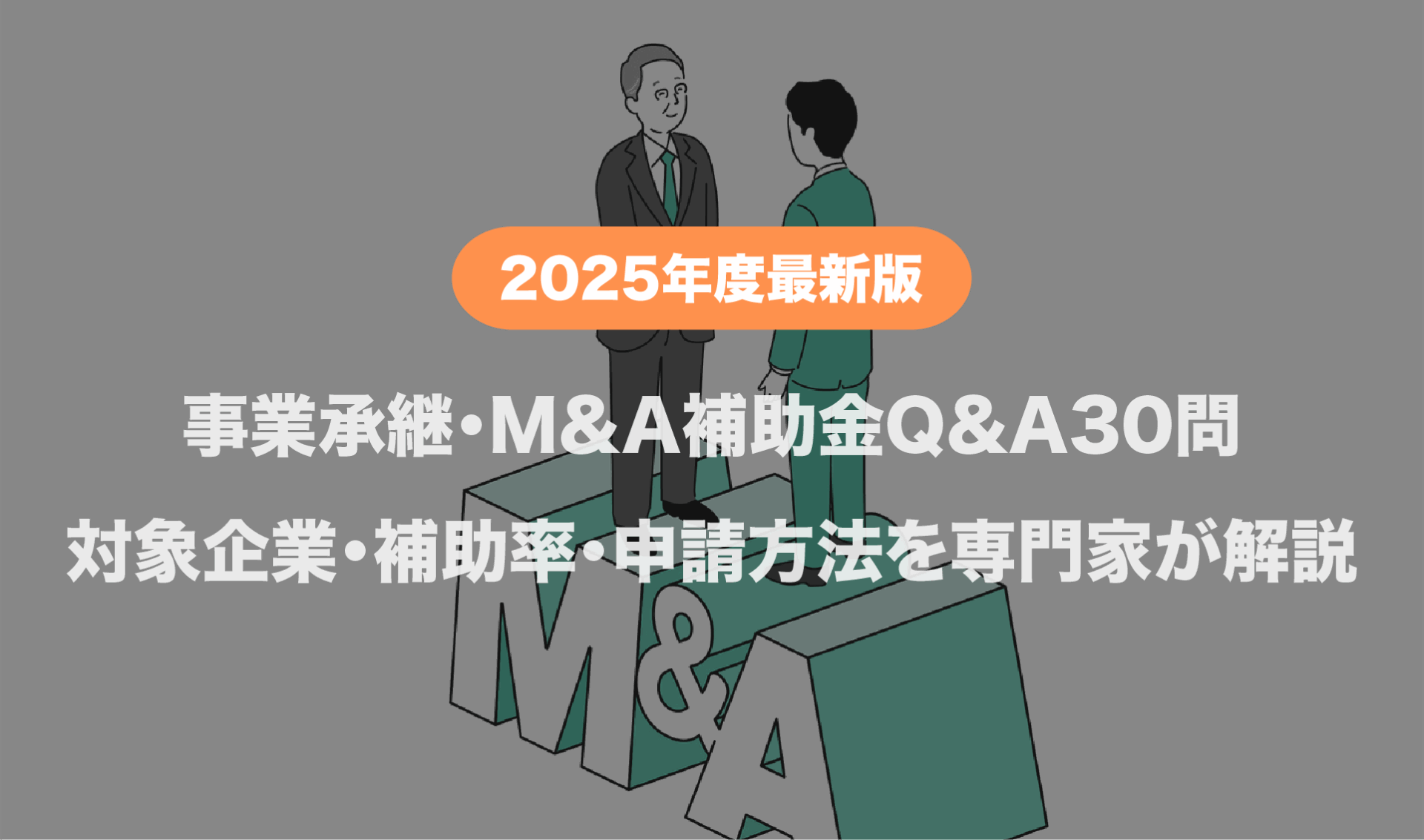【保存版】東京都の省エネ設備・フードロス対策補助金|要件・対象経費・申請手順まとめ
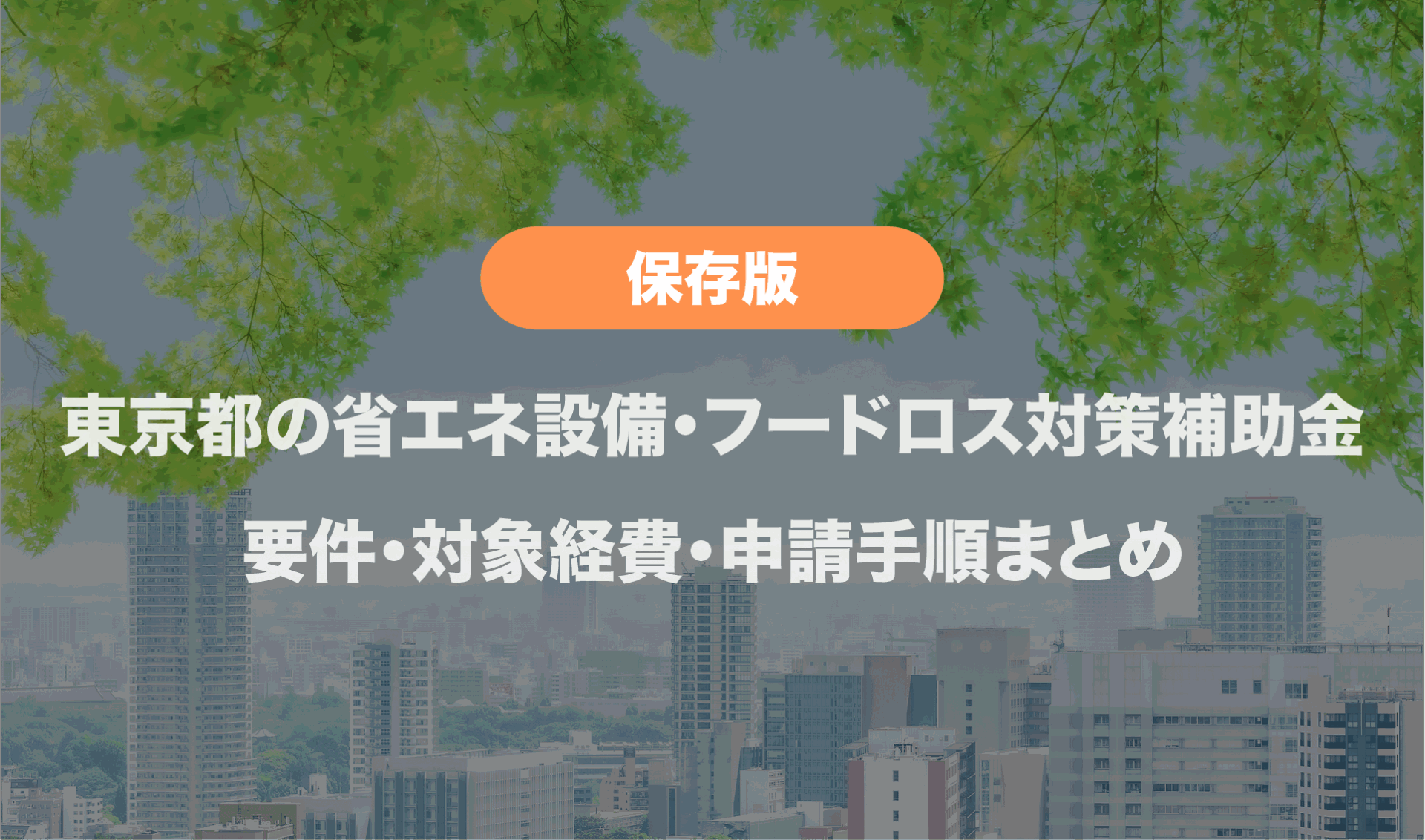
東京都では、中小企業等を対象に、環境対策を支援するための助成金制度が複数実施されています。本記事では、特に注目度の高い以下の2つの制度について、その目的、対象、補助内容、申請方法などを詳しく解説します。
• 「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業」(省エネ対策)
• 「小売ロス削減総合対策補助金」(フードロス対策)
これらは、中小企業のコスト削減や競争力強化に直結する魅力的な制度です。ぜひ、自社の取り組みに活用できないか検討してみてください。
目次
ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業とは?
この補助金は、東京都が目指す「2050年までにCO2排出を実質ゼロにする」という目標の実現をサポートする制度です。
古くなった設備を省エネ性能の高いものに入れ替えたり、使い方を工夫して省エネを進めたりする中小企業に対し、費用の一部が補助されます。
光熱費の削減だけでなく、環境への取り組みとして企業イメージの向上にもつながるのが特長です。
対象事業者と対象設備
この制度は、都内に事業所がある中小企業をはじめ、医療法人や社会福祉法人なども対象となります。
飲食店や工場、小売店、福祉施設など、さまざまな業種で活用することができます。
補助の対象となるのは、業務用の空調設備やLED照明、高効率ボイラー、断熱性能の高い窓、冷凍・冷蔵設備など。
さらに、人感センサーの導入や、スイッチのエリア分けといった省エネのための運用改善も対象になります。
助成を受けるための条件とCO2削減の目安
この補助金を利用するには、設備の導入や運用の見直しによって、CO2の排出量をある程度削減できる見込みがあることが条件となります。
具体的には、次のいずれかに当てはまる必要があります。
- 年間で28トン以上のCO2を削減できる計画(大幅削減プラン)
- 省エネ診断の結果に基づき、3トン以上、または30%以上の削減が見込める計画
- 自社で立てた計画で、3トン以上、または30%以上の削減が見込める場合
また、事業所の規模などによっては、東京都に「地球温暖化対策報告書」の提出が必要になることもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
補助の割合や上限金額、対象となる費用について
補助の割合や上限金額は、CO2削減の計画内容によって変わります。主なパターンは以下の通りです。
- 年間28トン以上の削減が見込める場合:補助率は3/4(自己負担は1/4)、補助の上限は4,500万円
- 省エネ診断の結果に基づく計画:補助率は2/3、上限は2,500万円(大幅な削減が見込める場合は、補助率3/4・上限5,000万円に引き上げられるケースもあります)
- 自社で立てた計画の場合:補助率は2/3、上限は1,000万円
補助の対象となる費用は、設計費、設備の購入費、設置工事費などです。
ただし、消費税や古い設備の撤去費用だけを補助対象にすることはできませんので、ご注意ください。
申請から採択までの流れと注意点
申請は原則オンラインで行い、2025年度は年5回の募集期間が設けられています。先着順ではなく、公募期間中に提出された申請書をもとに、審査・抽選によって採択が決まります。ただし、交付決定を受ける前に機器の発注や工事を始めてしまうと補助対象外になってしまうため、スケジュール管理には十分注意が必要です。
審査では、「どの程度CO2削減が見込めるかを数字で示せているか」「実際に実行できる現実的な計画かどうか」などが評価されます。省エネ診断を事前に受けておくと、計画の信頼性が高まり、審査でも有利になるでしょう。また、同じ年度内に複数の事業所で同時に申請することはできないなど、制度上のルールもあるため、公募要項は事前によく確認しておくことをおすすめします。
補助金を活用するメリットとは?
この補助金を活用すれば、初期費用の最大3/4までを東京都が補助してくれるため、大きな設備投資でも取り組みやすくなります。補助を受けて高効率な機器へ更新すれば、光熱費の削減や業務効率の向上につながり、投資回収までの期間も短縮されるでしょう。
さらに、環境に配慮した取り組みを行っている企業として、取引先や顧客からの評価が高まることも期待できます。長期的には、エネルギー価格の高騰やカーボンプライシングへの備えとしても有効です。単なるコスト削減にとどまらず、自社の成長とブランド価値向上にもつながる制度といえるでしょう。
小売ロス削減総合対策補助金とは?
食品の売れ残りや賞味期限切れによる廃棄を減らすために、東京都が用意している補助金制度です。対象は、都内で食品を販売している中小の小売事業者。最大1,500万円までの補助を受けることができ、8つの対策メニューの中から自社に合った取り組みを選んで申請できます。
対象となる事業者と主な条件
対象となるのは、スーパーやコンビニ、惣菜店、ベーカリーなど、食品を一般消費者向けに販売している中小の事業者です。
申請にはいくつかの条件があり、たとえば「賞味期限前食品の廃棄ゼロ行動宣言」に賛同することや、他の補助金と重複して申請しないことなどが求められます。
補助メニューの内容(例)
補助の対象となる取り組みは、次のようなメニューがあります。
- 需要予測システムの導入:1店舗あたり上限250万円、補助率は1/2
- 急速冷凍機の導入:上限300万円/店舗、補助率1/2
- フードバンクへの食品寄贈の支援:上限14万4,000円まで全額補助
- コンポスト設備の導入:上限100万円/店舗、補助率1/2
- 独自のアイデアによる取り組み(提案型):事前相談が必要、上限250万円/店舗
これらの補助では、機器の購入費だけでなく、設置工事や導入後の運用にかかる費用なども対象になります。
申請の流れと注意点
この補助金は、2024年5月30日から2025年12月31日まで申請を受け付けています。
随時受付(先着順)で、申請方法はメールまたは郵送です。必要な書類は公式サイトからダウンロードでき、提出先もそちらで確認できます。
ただし、予算には限りがあるため、予定件数に達し次第受付が終了する可能性があります。興味がある方は、できるだけ早めの準備・申請をおすすめします。
申請書では「どのくらい食品ロスを減らせるか」などの効果を、できるだけ数値で示すことが求められます。さらに、導入したあとに継続して運用していける体制があるかどうかも、審査の大切なポイントです。
また、メニュー5(フードバンクへの寄贈)やメニュー8(独自提案型)のように、事前に相談や協定が必要なケースもあります。制度の詳細は公募要項をしっかり確認して、計画的に進めていきましょう。
補助金を活用するメリットとは?
この補助金を活用すれば、廃棄コストの削減だけでなく、新しい販売方法や商品の展開など、経営面でもさまざまなプラス効果が期待できます。たとえば、余った食品を急速冷凍して商品化したり、売れ残りを減らす仕組みを導入したりといった取り組みが現実的になります。
また、食品ロス削減への積極的な姿勢は、SDGsへの貢献として評価され、企業のイメージアップにもつながります。メディアに取り上げられたり、地域の信頼を得たりすることもあるため、「環境対策=コスト」ではなく、「経営改善のチャンス」と捉えて活用するのが賢い選択です。
まとめ
東京都の省エネ・食品ロス対策補助金は、中小企業の設備投資や経営改善をしっかり後押ししてくれる制度です。補助率が高く、支援メニューも豊富なので、実際の現場でも活用しやすい内容になっています。
将来的なエネルギーコストの上昇や、脱炭素社会への対応に備える意味でも、こうした制度を上手に活用することは大きなメリットになります。気になる方は、早めに公募要項をチェックして、準備を進めてみてはいかがでしょうか。
パートナー企業