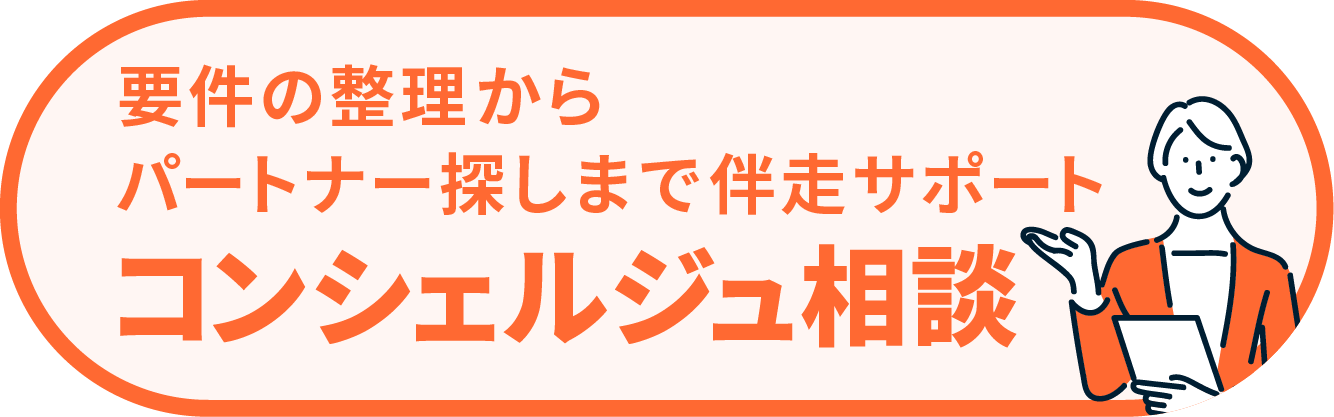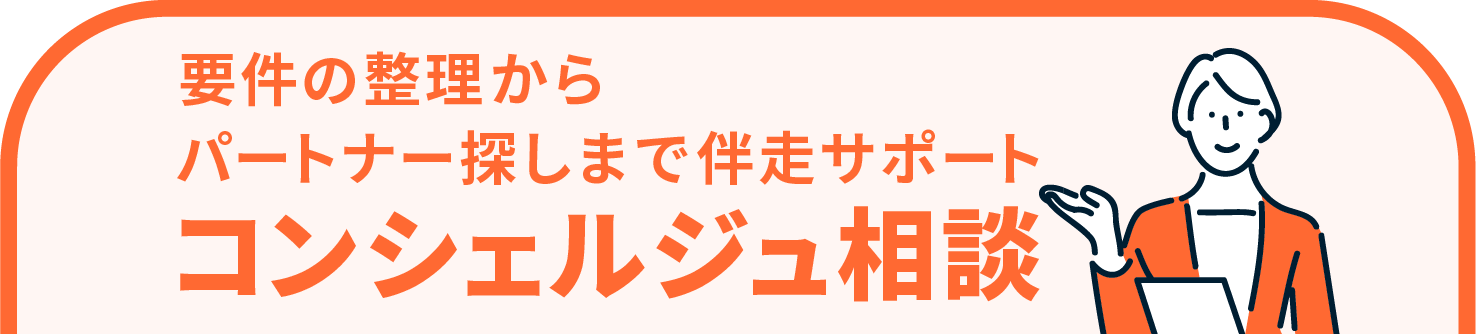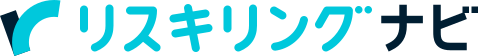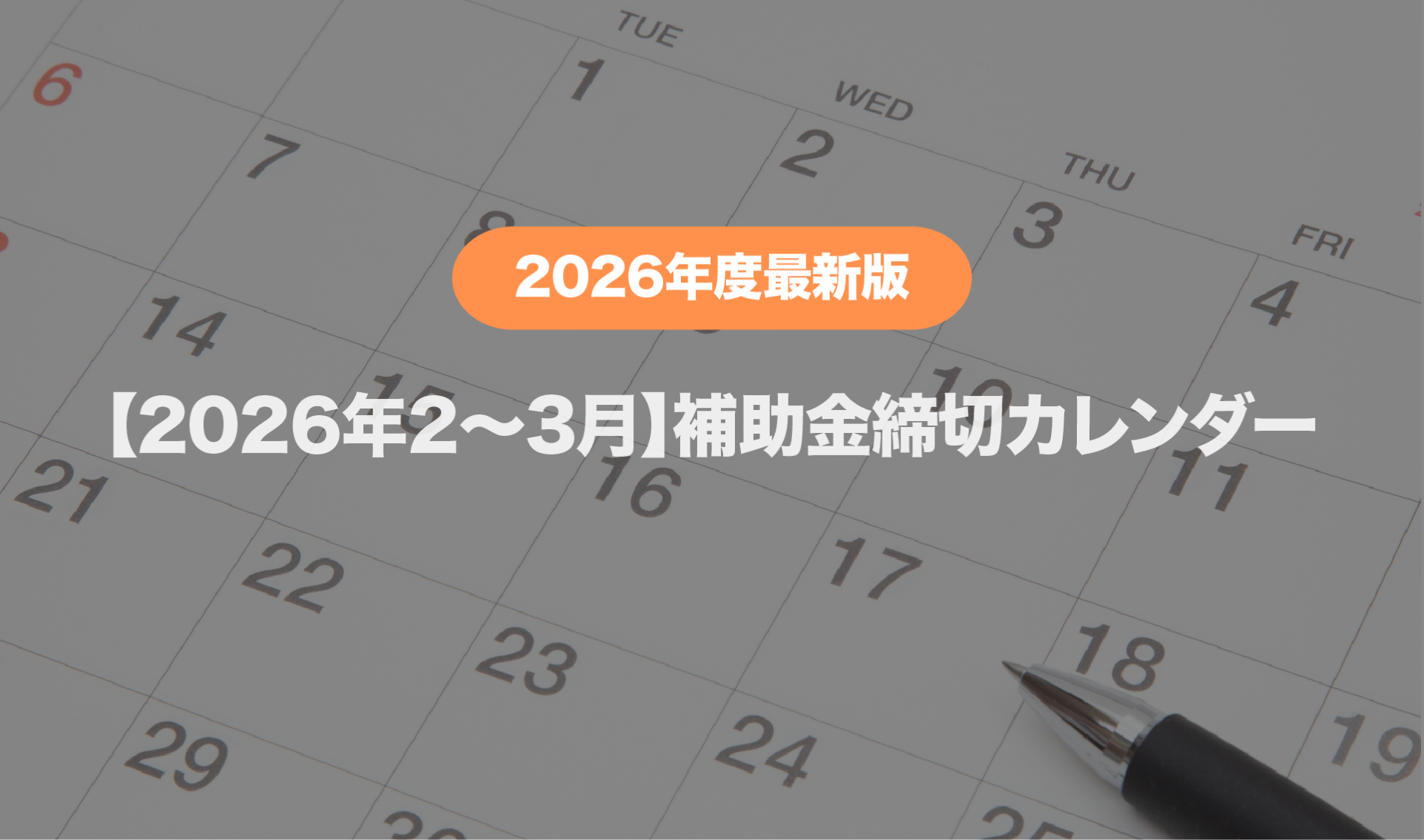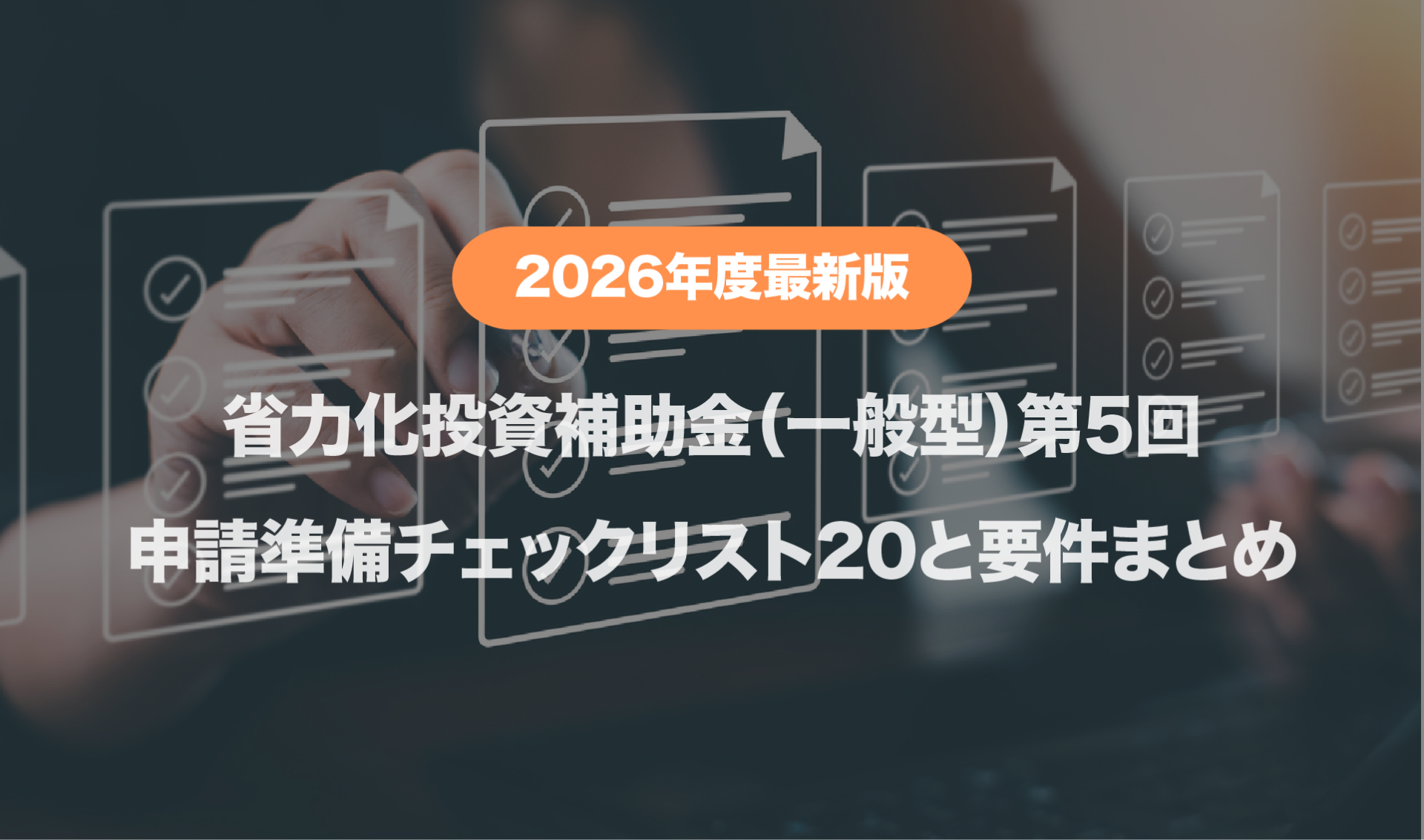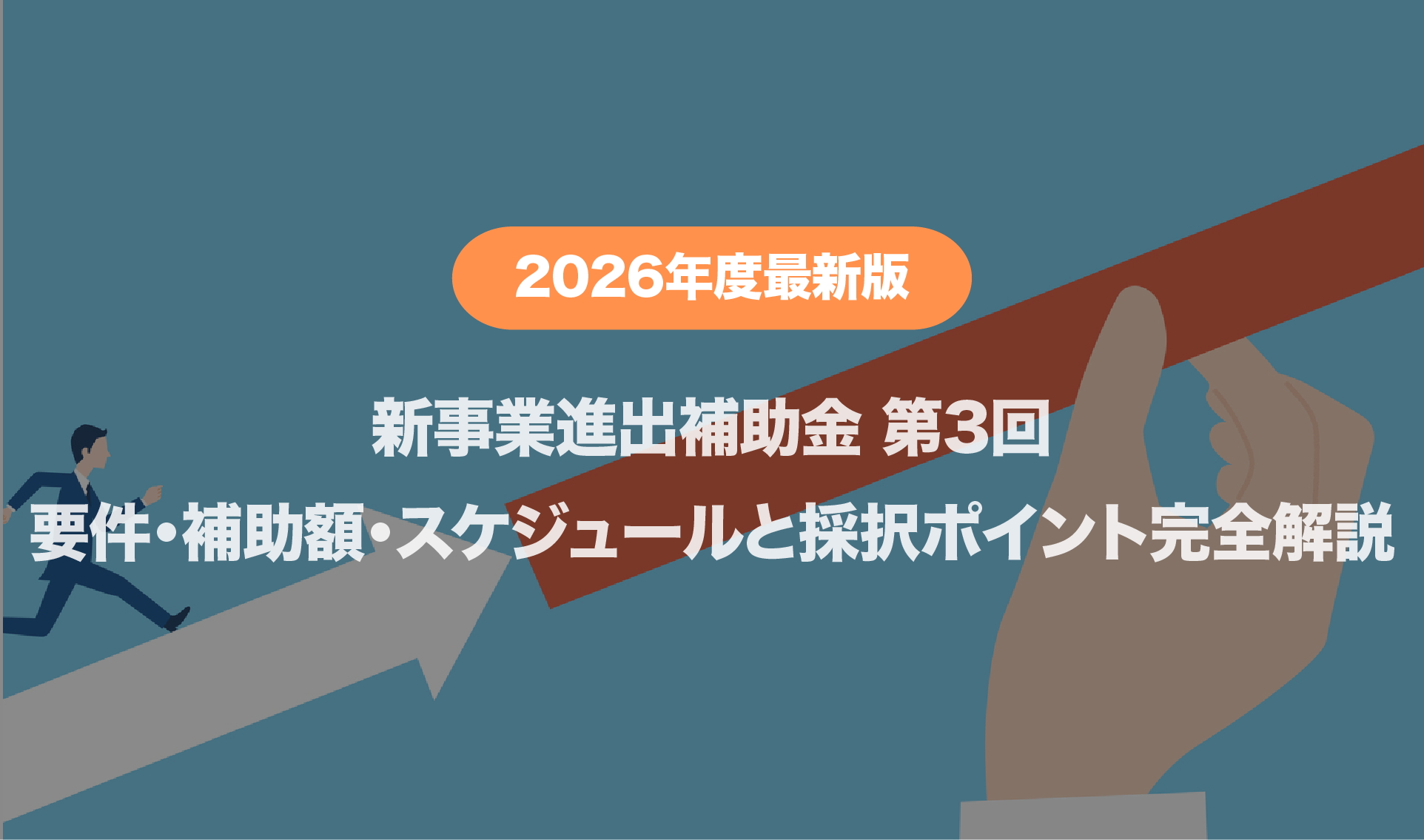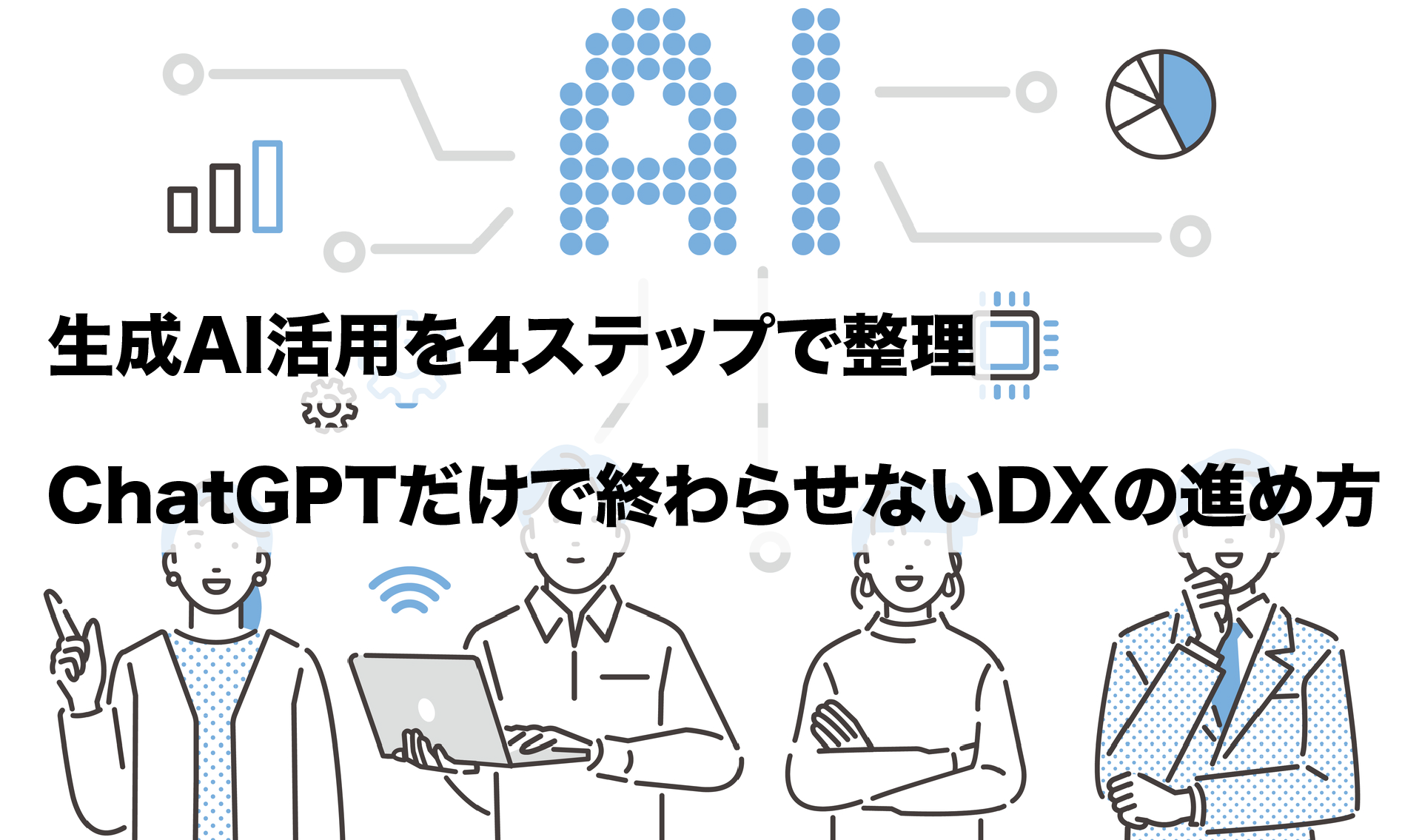eラーニングシステムの活用方法は?メリットや選び方のポイントも解説

eラーニングシステムは、オンライン上での研修や講習を行う際に使用するシステムのことです。この記事では、eラーニングシステムの概要や活用方法、導入する際に押さえておきたいポイントなどについて解説しています。後半では、おすすめのeラーニングシステムも紹介しますので、これからシステムを導入しようとしている企業の担当者はぜひ参考にしてください。
目次
eラーニングシステムとは
eラーニングシステムとは、研修や講習をオンライン上で提供・管理する際に使用するシステムのことです。そもそもeラーニングとは、インターネットを活用してパソコンやスマートフォンなどから学習する学習形態のため、eラーニングシステムはその学習に欠かせないシステムだと考えてください。
なお、eラーニングシステムは、「学習管理システム」と「学習教材」から構成されています。学習管理システムとは、オンライン上で研修や講習などを行うためのプラットフォームです。そして、学習教材は実際に研修・講習で使用されるテキストや動画などのことです。
eラーニングシステムは、学習者の管理はもちろん、教材の管理や進捗状況の管理、成績や評価のチェックもできるなど、幅広い情報を一元管理できるため、eラーニング運営担当者の負担を軽減してくれる点が特徴です。
eラーニングシステムの効果的な活用方法

eラーニングシステムの活用方法はさまざまです。ここでは効果的に活用するための具体的な方法を紹介します。eラーニングシステムの導入を検討しているものの、どのようにして活用すればいいのかいまいちわからないといった人はぜひ参考にしてください。
研修前の事前学習
研修を行う際の事前学習にeラーニングを活用できます。たとえば、研修で学ぶ内容に関連する基礎知識を事前にeラーニングで学べるようにしておけば、研修をよりスムーズに行えるでしょう。また、研修後にはeラーニングシステム上でテストを実施し、一定のレベルに達しているかチェックすることも可能です。もし一定のレベルに到達していなければ、個別にフォローできます。
OJTと組み合わせた新人研修
新入社員の教育にOJTを取り入れている企業は多いと思われますが、OJTにeラーニングを組み合わせることも可能です。たとえば、OJTで学んだことをeラーニングで復習できるようにすれば、知識やスキルが定着しているのか確認できます。また、業務で必要となる知識などを事前に学習できるようにすることでOJTの担当者もスムーズに教育できるでしょう。
ナレッジ共有
eラーニングシステムの中には、教材やマニュアルを作成・共有できるものもあるため、業務で役立つ知識やノウハウを資料としてまとめ、共有することもできます。また、動画作成や編集に対応しているシステムであれば、動画による情報共有も可能です。
eラーニングシステムを選ぶ際のポイント

ここではeラーニングシステムを選ぶ際に押さえておきたいポイントを紹介します。eラーニングシステムは各社から提供されているため、どれを選べばいいのか迷ってしまう人が多いのではないでしょうか。選ぶ際のポイントを理解することで、自社にあったシステムを見つけやすくなります。ぜひ参考にしてください。
学習コンテンツの豊富さ
eラーニングシステムによっては、膨大な数の学習コンテンツを用意しているケースもあります。コンテンツが豊富であるかどうかはチェックすべきポイントです。特に、自社内に学習教材がないような場合は、ベンダーが提供するコンテンツを使用することとなります。テキスト形式のものや動画を活用したものなどさまざまな種類のコンテンツがあるため、どのような形式かも確認しておくことをおすすめします。
自社のニーズに適しているか
eラーニングシステムは各社から提供されており、それぞれ機能や特徴が異なるため、自社のニーズに適しているかどうかを確認しておきましょう。たとえば、既存の学習教材を活用したい場合、コンテンツの豊富さよりも、既存コンテンツのアップロードに対応しているかどうかが重要です。また、自社でコンテンツを作成したい場合、eラーニングシステム上での作成が可能かどうか、作成できる場合は動画やテキストなど、どのような種類のコンテンツを作成できるのかといった点をチェックしておきましょう。
扱いやすさ
いくら多機能で便利なシステムでも、扱いにくいと十分に活用することができませので、操作性もチェックしておきましょう。たとえば、既存の学習教材をドラッグ&ドロップで簡単にアップロードできるか、学習教材を作成する際にテンプレートが用意されているかといった点が挙げられます。特にITツールを苦手としている人がいる場合、扱いやすさには注意しなければなりません。
社員の学びをサポートする機能があるか
eラーニングシステムの導入は、オンライン上での学習を通して社員のスキルアップにつなげることが目的となります。そのため、システム上に社員の学びをサポートし、成長へとつなげられる機能があるかどうかが大切です。受講者に対してリマインドしたり、進捗状況の確認ができたりする機能がついていれば、研修への参加忘れや課題の提出漏れなどを防げるでしょう。また、テスト機能があれば、学習したことが定着しているか確認できます。
ユーザー数制限
システムによってさまざまなプランが用意されており、中にはユーザー数が制限されているケースもあります。自社でどのくらいの人が利用するのかは事前に把握しておきましょう。ユーザー数制限を超えてしまったために、さらにコストがかかってしまうといった事態を回避できます。
eラーニングシステムの注意点
オンライン上での学習が可能となるeラーニングシステムは、社員の成長を促進するためにも、研修担当者の業務負担を軽減するためにも役立つものですが、いくつかの点に注意しなければなりません。
まず、技術の習得には適していません。eラーニングはオンライン上での学習となるため、実際に何かに触れて作業を行うことはできません。動画視聴を通して学ぶこともできますが、技術習得を目指すのであれば、対面での学習が必要となります。
また、学習へのモチベーションは社員個人に依存する点にも注意しなければなりません。たとえば、動画を再生していても実際に画面の前で視聴しているかどうかはわからないでしょう。そのため、研修後にはテストを実施するなど、学習者が真面目に取り組むような工夫が求められます。
おすすめのeラーニングシステム

ここではおすすめのeラーニングシステムを紹介します。eラーニングシステムといっても、その種類はさまざまであり、機能もシステムによって異なります。どれを選べばいいのか迷ってしまうといった方はぜひ参考にしてください。
SAKU-SAKU Testing
SAKU-SAKU Testingは、株式会社イー・コミュニケーションズが提供するeラーニングシステムです。これまでに1,500社以上で利用されており、1ヶ月に20万IDが利用されているなど、実績は申し分なしといえます。1つのIDは330円/月から利用できるため、コストを抑えたい企業にもおすすめです。
また、「マニュアル不要で誰でも操作ができる」というコンセプトに基づいて開発されたシステムであるため、受講者の管理や教材の管理なども行いやすくなっています。
参考:SAKU-SAKU Testing | 株式会社イー・コミュニケーションズ
Schoo for Business
株式会社Schooが提供するSchoo for Businessは、7,000本以上の動画を視聴できるeラーニングシステムです。生放送による授業も行っているため、授業中に気になる点を講師に直接質問することもできます。スマートフォンやタブレット端末など、マルチデバイス対応であるため、オフィスはもちろん外出先やリモートワーク中の自宅などからも利用可能です。
動画コンテンツの講師は各業界のトップランナーが務めており、ビジネススキルやWebサービスの開発スキル、ITスキルなどさまざまなジャンルについて学べます。
参考:Schoo for Business | 株式会社Schoo
CodeCamp
CodeCampは、コードキャンプ株式会社が提供するITやWeb関連のスキルアップに役立つシステムです。WebマスターやJavaマスター、Rubyマスター、アプリマスターといった各領域に特化したコースのほか、内定者向けプログラミング研修や新卒社員向けプログラミング研修など属性に応じた研修にも利用可能です。
オンライン上では、進捗状況や課題の提出状況、受講生の評価なども管理できるため、管理担当者の手間も軽減されます。
これまでにIT企業を中心に300社以上で導入されているなど、実績も豊富です。
ひかりクラウドスマートスタディ
システムを提供する企業への信頼度を重視している方には、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)が提供するひかりクラウドスマートスタディがおすすめです。
こちらのシステムでは、自社教材による研修を行えるほか、研修後にはドリルを使った理解度チェックテストも行えます。
また、メッセージ機能がついているため、1対1でのコミュニケーションも可能です。たとえば、ドリルでの理解度チェックの成績が良くなかった社員に対して個別でコミュニケーションをとりフォローすることもできます。さらに、管理者や受講生をグループ分けすることができ、管理者に応じた権限の付与もできるため、管理がやりやすくなるでしょう。
そのほかにも、契約者専用でサポートセンターが用意されているため、トラブルが発生した時でも安心です。
参考:ひかりクラウドスマートスタディ | 東日本電信電話株式会社
AirCourse
AirCourse は、KIYOラーニング株式会社が提供するeラーニングシステムです。システム内には、4000本の動画が用意されており、階層別・テーマ別の研修などにも活用できます。
また、コンテンツの中には、個人情報保護法や情報セキュリティ、ハラスメントなどを学習できるものもあるため、業務に関連したスキルだけでなく、社会人として身につけておくべきスキルや知識を学ぶことも可能です。自社教材を使ったコースの作成にも対応していることから、自社教材とシステム側で用意している動画などを組み合わせた研修も実施できるでしょう。
初期費用0円で、1名あたり月額200円から利用できるため、コスト面を重視している人にもおすすめです。
Smart Boarding
教育研修を手掛ける株式会社FCEトレーニング・カンパニーが提供するのがSmart Boardingです。
こちらのシステムは、350種類以上の動画を視聴できるほか、学んだことを実践するライブ型のオンラインレッスンも受講できます。そのため、インプットに偏ることなく、適宜アウトプットを行い知識やスキルの定着を図ることが可能です。また、自社で作成した既存のコンテンツをアップロードすることもできます。
システムは1ヶ月980円/1IDで利用可能です。
参考:Smart Boarding | 株式会社FCEトレーニング・カンパニー
セキュリオ
LRM株式会社が提供するセキュリオは、情報セキュリティの研修に特化したシステムです。
具体的には、個人情報保護研修やマイナンバー研修、情報セキュリティ研修、リモートワーク実施に伴い注意することなど、企業にとって欠かせないテーマについて学べます。また、学習だけでなく、理解度テストも実施可能です。情報セキュリティに関する研修を行いたいものの、自社で教材を作成するのが難しいという企業は少なくないでしょう。そのようなときに役立つのがセキュリオです。
なお、セキュリオでは、自社で作成した既存コンテンツのアップロードにも対応しているため、通常のeラーニングシステムとしても活用できます。
グロービス学び放題
グロービス学び放題は、株式会社グロービスが提供するeラーニングシステムです。MBA講座などで有名な同社ですが、こちらのシステムも6,000社以上の導入実績を誇るなど、多くの企業で利用されています。受講できるコースは1,800以上で、基礎知識の習得から、ビジネスリーダー向けの実践的な内容まで多角的に勉強できる点が特徴です。ビジネス系のテーマはもちろん、ITやDXをテーマにしたコースもあります。受講生の進捗管理や受講の促進、受講支援などの機能も備わっているため、管理者にとっても利便性の高いシステムだといえるでしょう。
Aidemy Business
株式会社アイデミーが提供するAidemy Businessは、DX人材の育成をテーマにしたeラーニングシステムです。Python入門やディープラーニング基礎など初心者を対象としたコンテンツも用意されているため、新入社員向けの研修などにも活用できるでしょう。また、動画の視聴だけでなく、クイズを解きながら理解を深めていくものや実際にコーディングをしながら取り組むものなど、さまざまな形で知識・スキルの習得を目指します。専任担当者によるカスタマーサポートも受けられるため、初めてeラーニングシステムを導入する企業にもおすすめです。
参考:Aidemy Business | 株式会社アイデミー
LearningWare
株式会社プロシーズが提供するLearningWareは、eラーニングはもちろん、集合研修の際にも利用できるなど、企業の学習・研修を一括で管理することができます。これまでの導入企業は2,400社、利用者は100万人を超えるなど、豊富な実績を誇ります。
Pマーク・ISMSを取得しているほか、2段階認証機能を備えているなど、セキュリティ面も安心です。さらに、英語や中国語など、合計30以上の言語に対応しており、動画は自動翻訳機能で字幕化されるため、多国籍な企業での導入にもおすすめです。
まとめ
今回は、eラーニングシステムの概要や選ぶ際のポイント、おすすめのシステムなどを紹介しました。eラーニングシステムは、「学習管理システム」と「学習教材」から構成されるeラーニングを提供するためのシステムのことです。集合研修の事前学習やOJTとの組み合わせ、ナレッジの共有など、さまざまな場面で活用可能なシステムとなっています。導入に当たっては、自社のニーズを把握し、コンテンツの量や操作性などをチェックしましょう。
パートナー企業