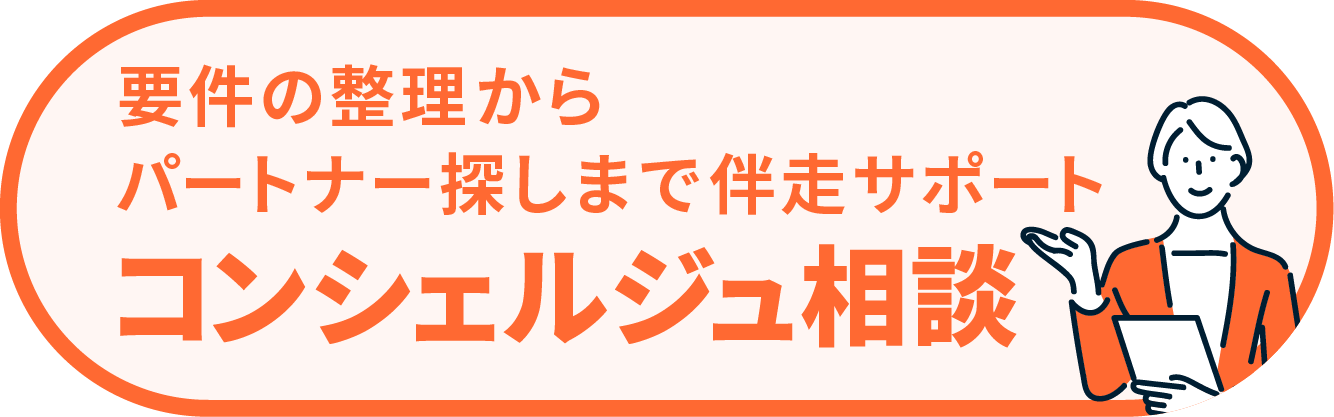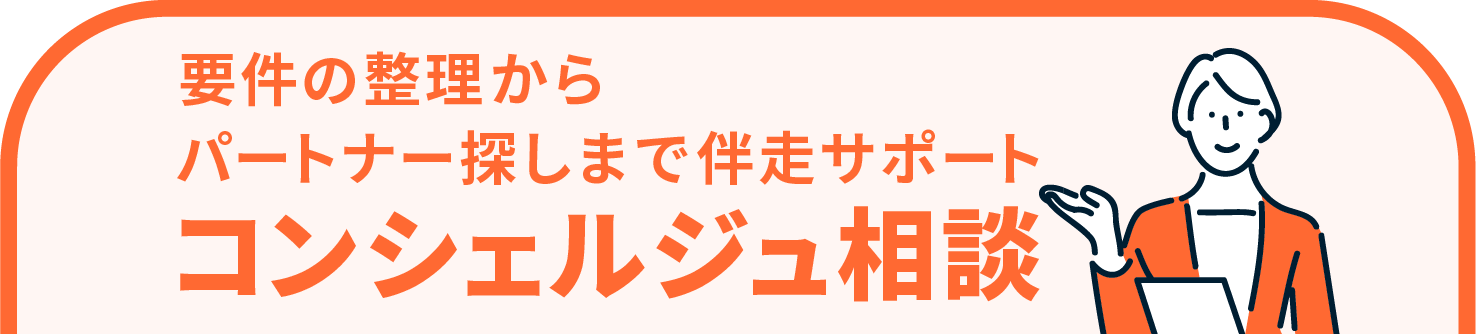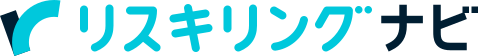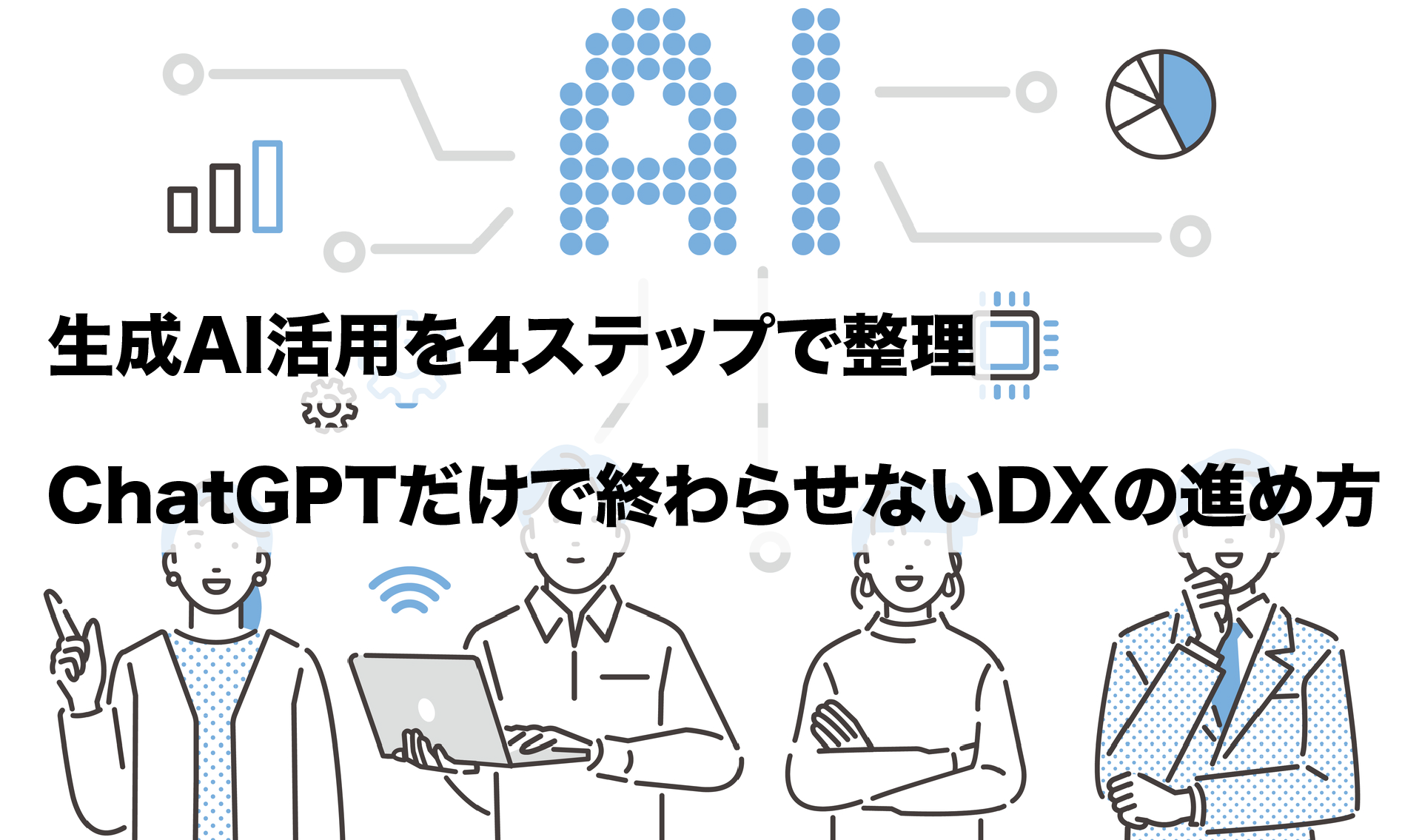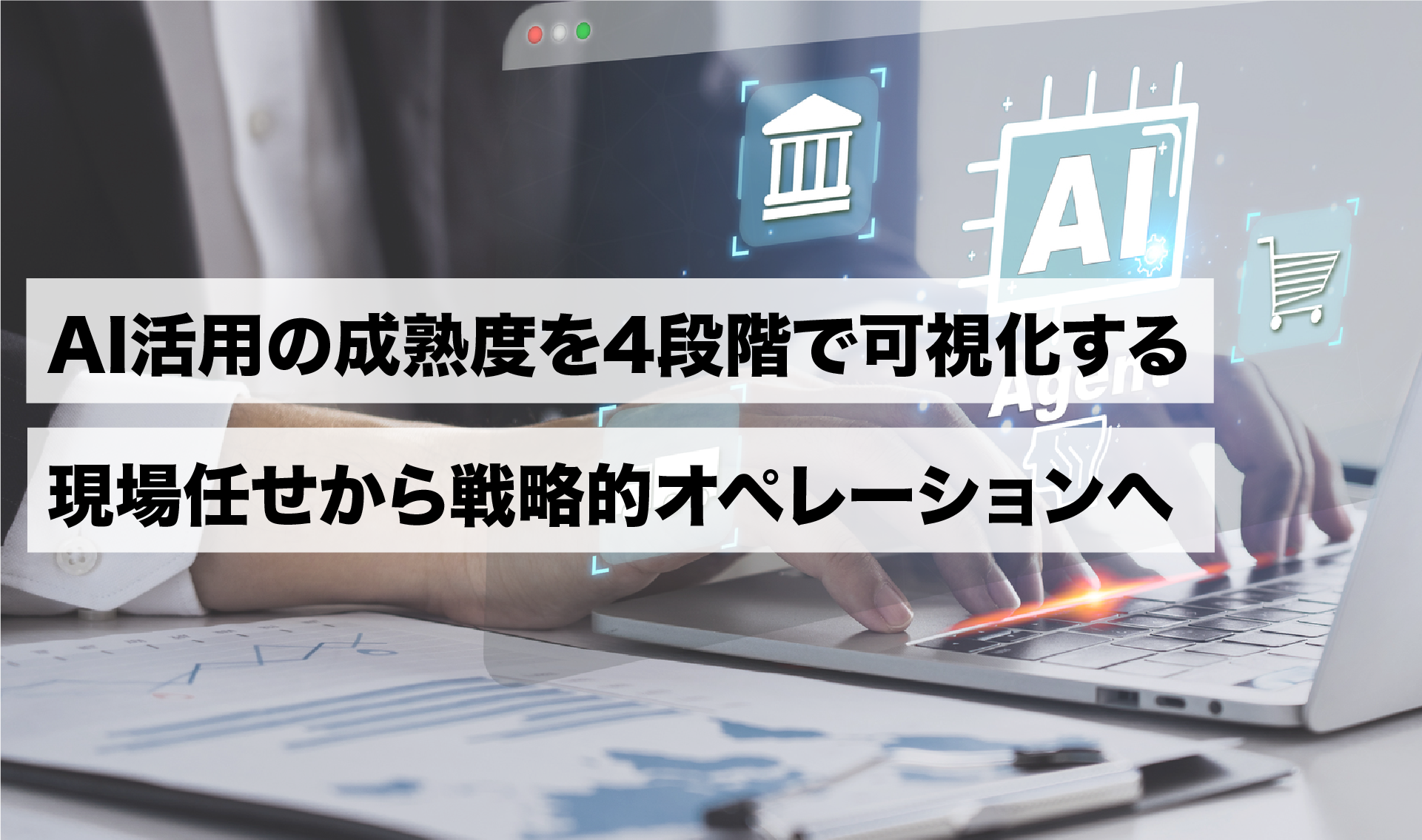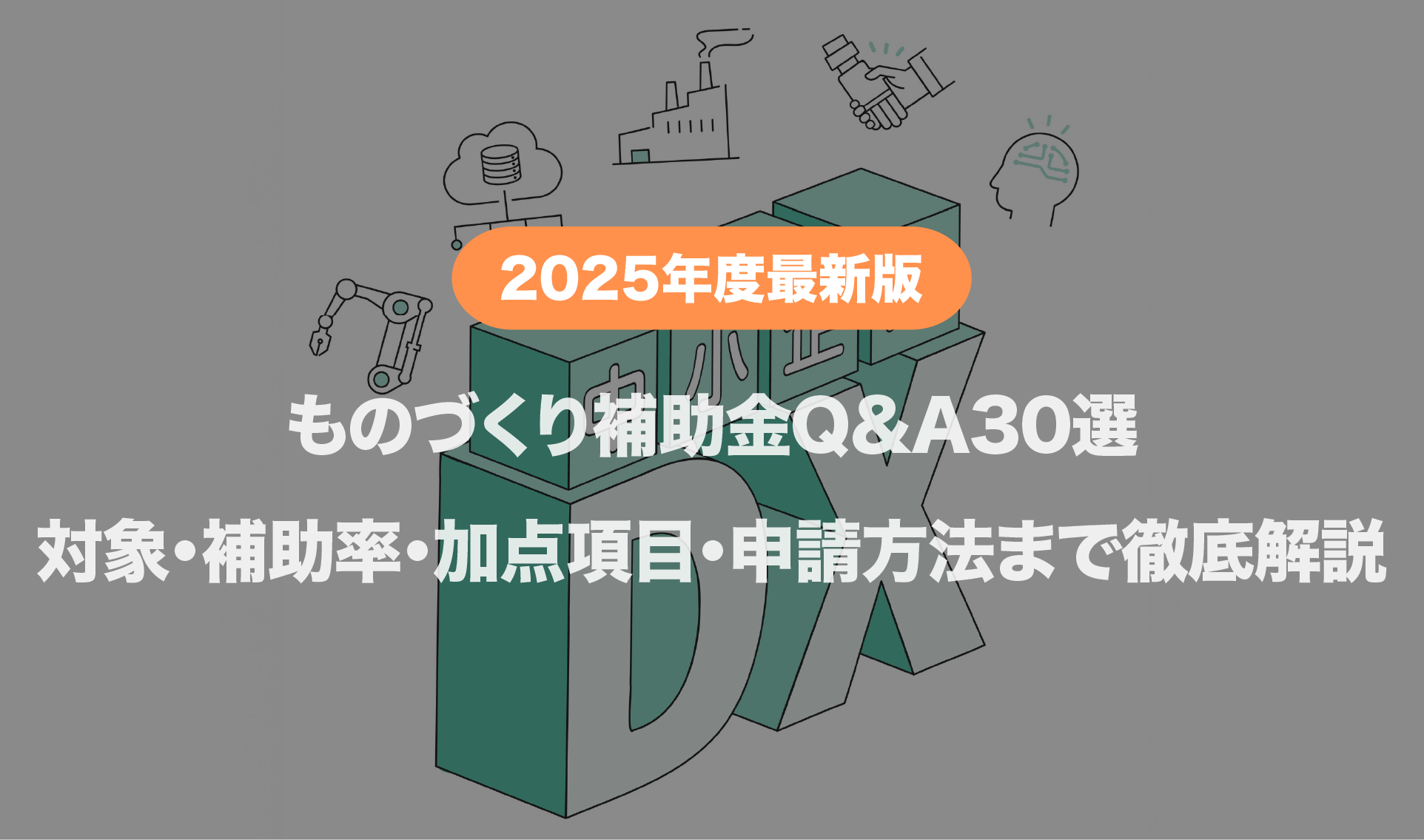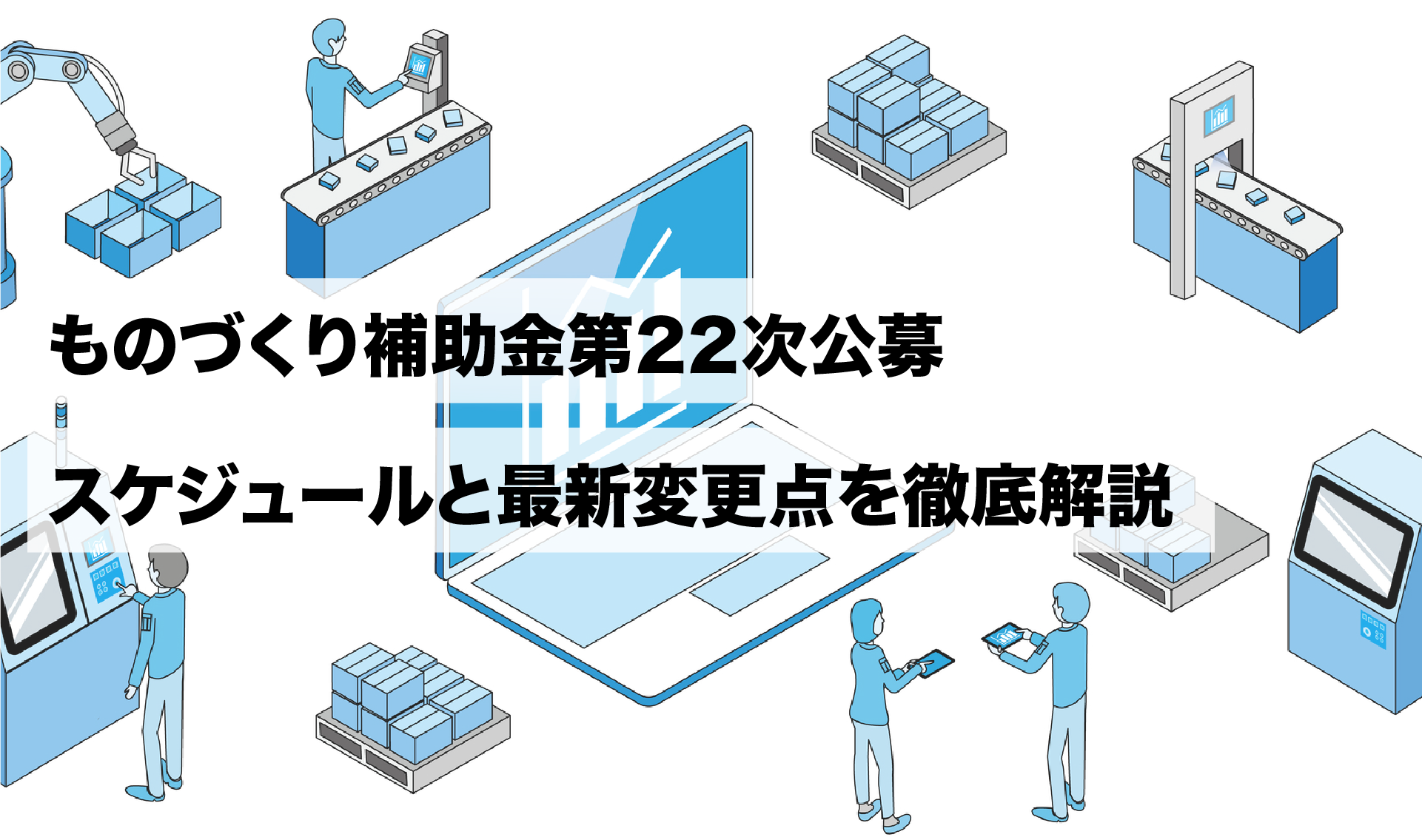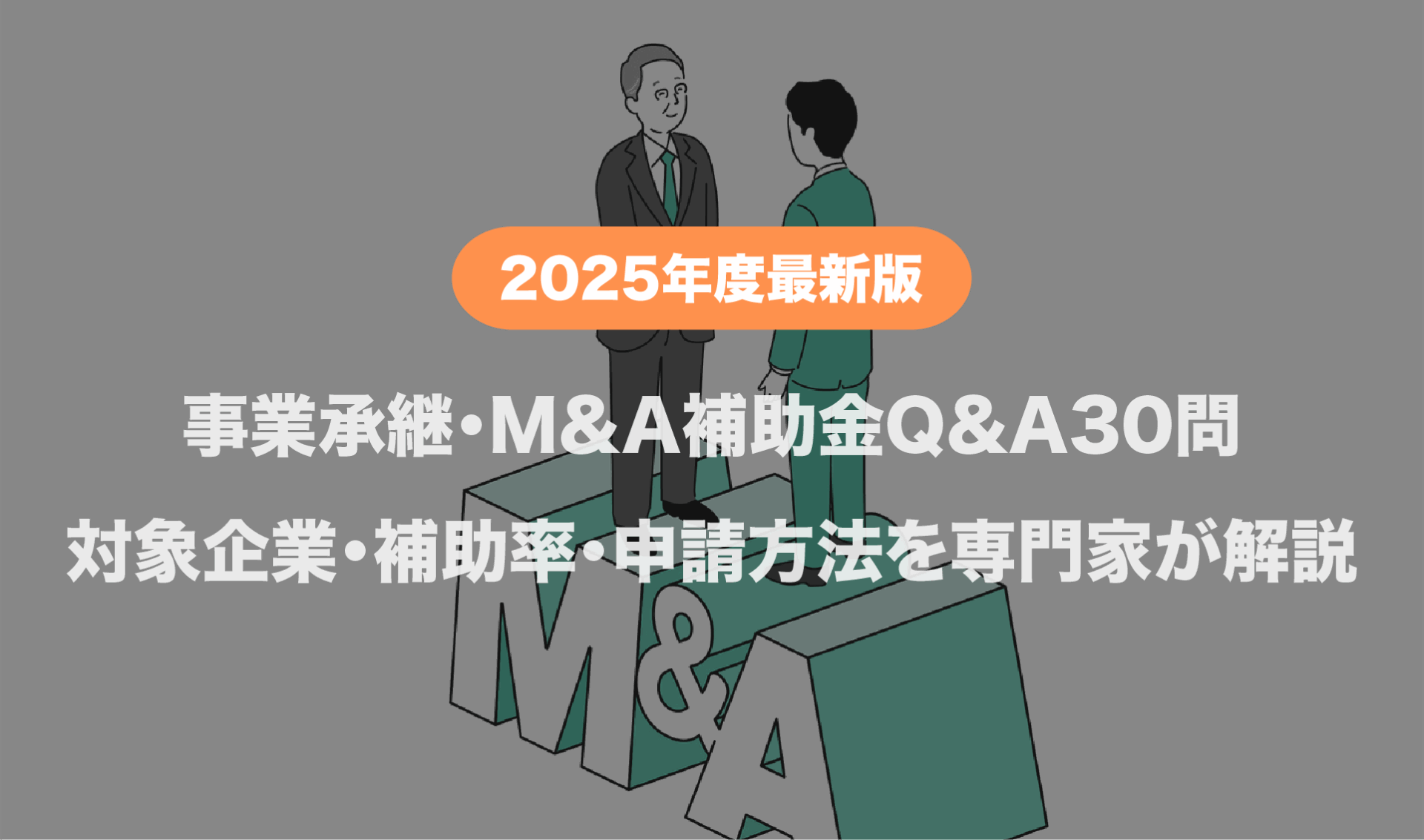人材育成研修の内容はどうする?3種類の手法と意識すべきポイントを解説
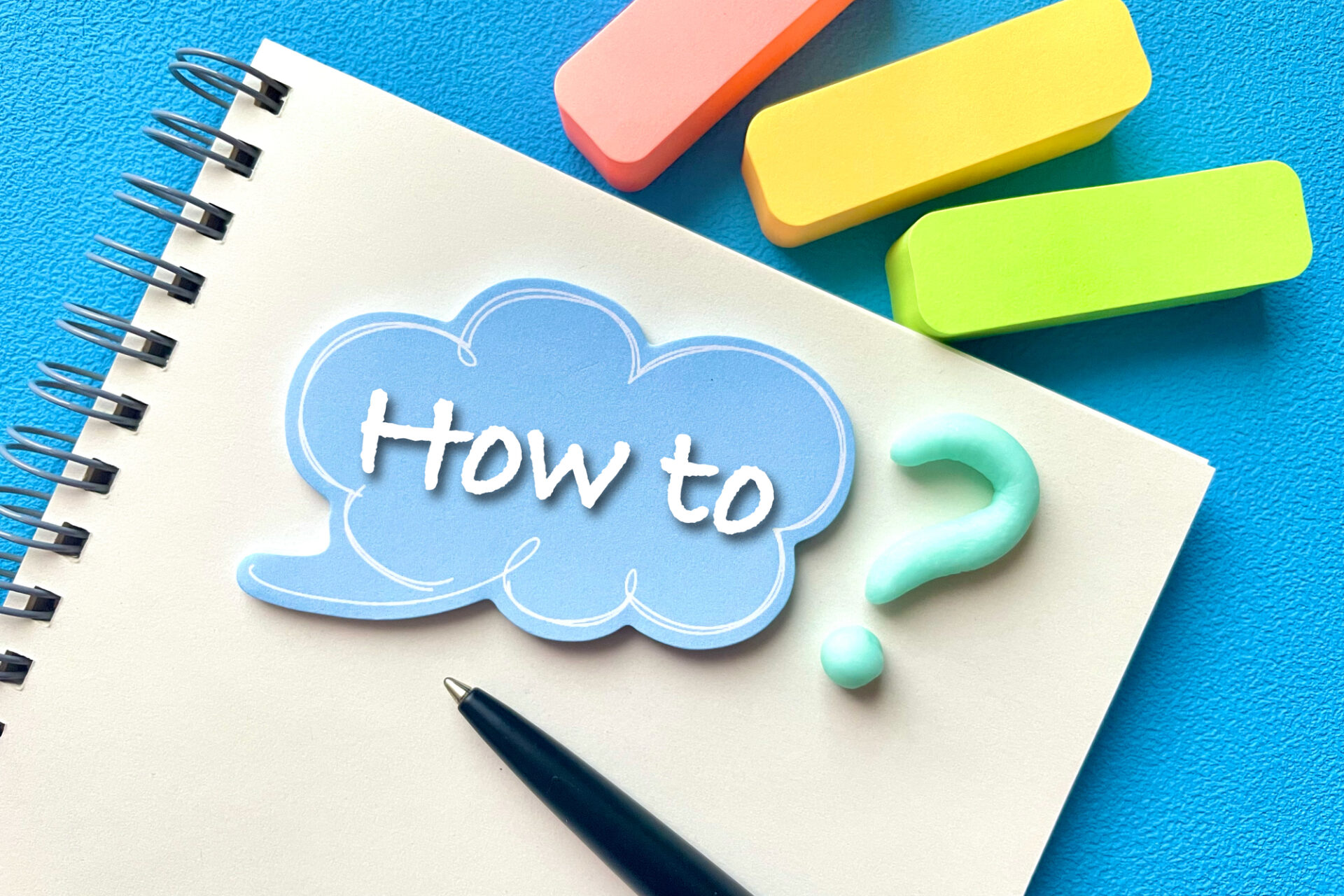
近年注目を集め、日々新しい手法が開発されている人材育成研修。その取り組み方も、企業によって千差万別です。
そのため、担当者にとって「人材育成研修をどのように構築すべきか」は大きな悩みのタネとなることも多いでしょう。
本記事では、人材育成の研修を考えるうえでのポイント、代表的な手法や進め方について解説していきます。
目次
人材育成とは?
人材育成とは、企業の中長期的な業績アップを目的として、社員のスキルや知識を伸ばす取り組みのこと。
近年、ビジネス環境における「IT化」や「労働力の減少」などの背景から、人材育成が企業の戦略としてますます重要視されるようになってきています。
人材育成の基本的な意味については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。 RE_17「人材育成の基礎」.docx
人材育成の研修内容を考える際のポイント
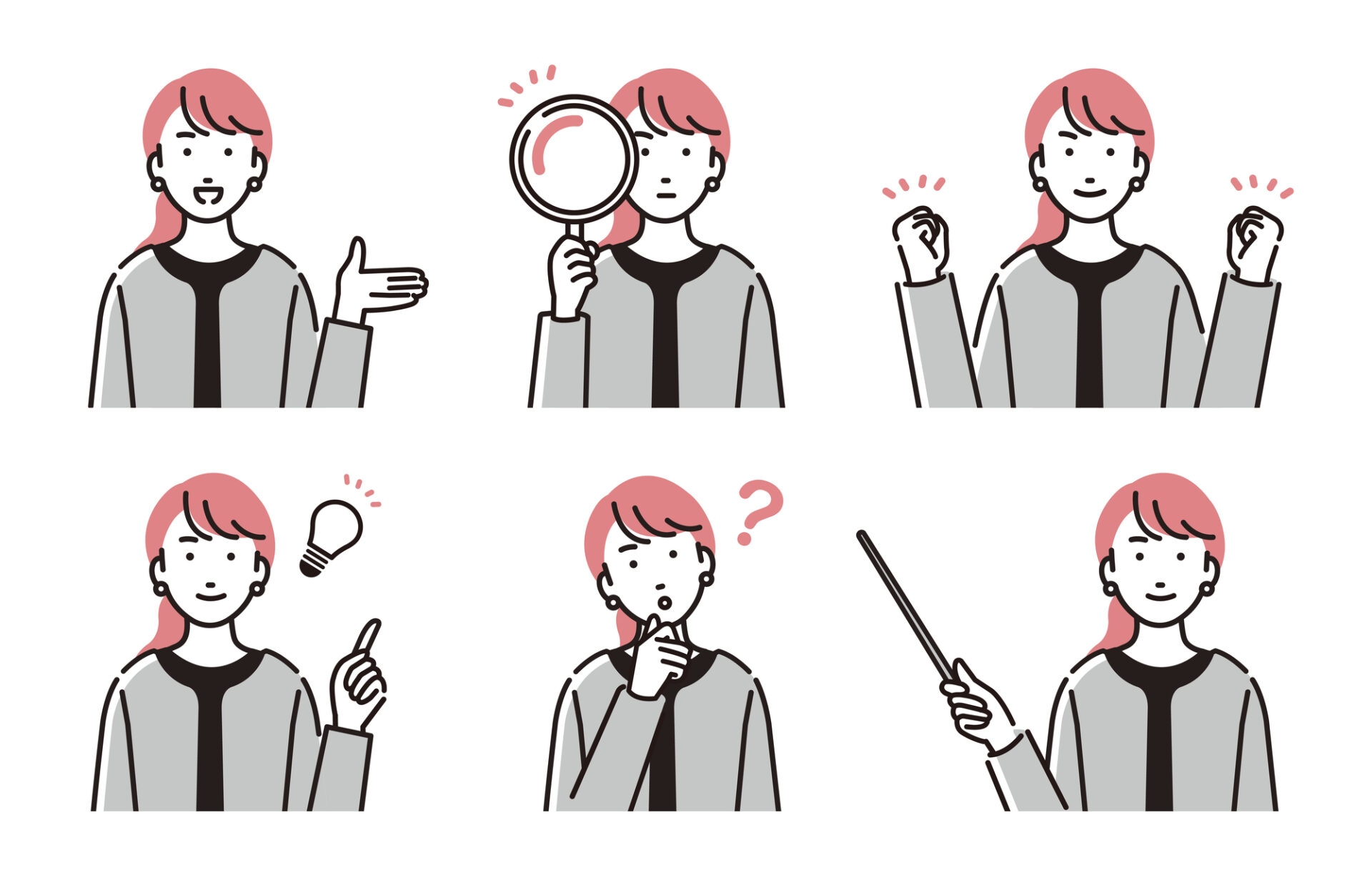
人材育成の研修内容を考えるにあたり、注意すべきポイントが3つあります。
- 目的を明確にする
- 社員の自発性を重視する
- 教える側にもフォローを行う
目的を明確にする
1つ目のポイントは、人材育成の目的を明確にすることです。特に、企業視点での最終目的を明文化し、人材育成に関わる社員全体に共有することが重要です。
人材育成は、成果が目に見えるまで長い期間がかかるうえ、多くの社員が日常業務の合間を縫って行わなければなりません。
そのため、現場の社員一人ひとりが人材育成の意義や価値を理解し、成長へのモチベーションを高めるためには、経営理念に基づいたゴールやビジョンを描き、伝えることが求められるのです。
社員の自律性を重視する
人材育成においては、社員に対して「接客」や「プログラミング」などのハードスキルだけでなく、「積極性」や「思考力」といったソフトスキルも育てる必要があります。
ここでポイントとなるのが、育成対象となる社員の自律性を重視するという点です。そのためには、本人による目標設定、挑戦を高く評価する制度などにより、マネジメント側からも、社員が自分から成長の機会を作りやすい環境を用意することが求められます。
教える側にもフォローを行う
人材育成によくみられる課題の一つが、教える側の指導スキルの不足です。特に、指導担当にあたる社員自身が「背中を見て学ぶ」文化の中でキャリアを積んできたような世代の場合、部下への指導やコーチングのスキルが足りないことも少なくありません。
したがって、指導担当となる社員に対しても、指導スキルのインプットができる環境を整える、時間を掛けて指導に取り組めるよう通常業務を削る、1on1ミーティングを設けるなど、必要に応じてフォローを行っていく必要があるでしょう。
人材育成研修の手法/内容

人材育成研修の手法には、大きく分けて以下の3つがあります。
- OJT(On the Job Training)
- Off-JT(Off the Job Training)
- SD(Self Development)
それぞれの意味と内容を、詳しく紹介していきます。
OJT(On the Job Training)
OJT(On the Job Training)とは、「現場で行う研修」のことです。
一般的には、上司から部下に対し、職場で訓練や実践を通してレクチャーやフィードバックを行います。直接実務に触れながらの学習となるため、セールスや接客など、知識よりも反復的なアウトプットが求められるような内容に向いています。
また、ともに働く社員間でのコミュニケーションが生まれ、人間関係を醸成できるというメリットもあります。
Off-JT(Off the Job Training)
Off-JT(Off the Job Training)とは、「現場の外で行う研修」のことです。
具体的な方法としては、会場を用意して社員を集めて行う集合型研修やオンラインで講義を配信するeラーニングなどがあります。
階級別研修や新入社員研修のように、必要な知識やスキルを体系的に教えるため、OJTに比べ、より短期間に効率よく知識を学習できるというメリットがあります。
SD(Self Development)
SD(Self Development)とは、「自己啓発」のことです。つまり、社員自らが学習の機会を作り、成長することを促進する手法です。
具体的には、書籍購入や資格取得の費用を補助する制度を用意したり、外部のセミナーを紹介したりする取り組みが挙げられます。
SDの利点としては、社員自身の自由度が高く、幅広い選択肢の中から学習内容を選べるため、広い範囲の内容を学べる、社員のモチベーションが高まるといった点があります。
人材育成研修の効果的な進め方は?

人材育成研修を効果的に進めるには、どのように進めればよいのでしょうか?
ここでは、以下の4つのステップを踏みながら、人材育成研修の基本的な進め方を解説します。
- 現状の課題を把握する
- 企業が求める人材のビジョンを定める
- 施策を計画し、実行する
- 取り組みの結果を評価する
現状の課題を把握する
最初に取り組むべきは、現状の課題を把握することです。それぞれの部署や社員が現在どのような役割でどのような業務を行っているのか、どんな課題を抱えているのかを把握します。
どんな職務にも、現場の社員にしかわからない不満や課題意識があるもの。それらを確認するには、社員から直接ヒアリングを行うことが望ましいです。具体的には、業務フローや労働時間、タスクの配分、スキルに見合った役割が与えられているかなどを中心に詳しく掘り下げを行うとよいでしょう。
企業が求める人材のビジョンを定める
課題を明確化できたら、その課題を起点にして「企業が求める人材」の要素を定めます。
現在の自社に不足する人材やスキルが明らかになれば、それを目標として具体的な施策の方向性を検討することができます。
ただし、前述した通り、この時点でも企業の経営理念や業績目標に立ち返って考えることが重要です。経営方針と人材のビジョンにズレがあると、計画全体の整合性が取れなくなってしまうので、できれば経営陣の意見も交えて決定することが望ましいでしょう。
施策を計画し、実行する
人材育成研修の具体的な施策を計画し、実行していきます。
計画を立てる際のポイントは、目標達成の客観的な指標と期限を明確化すること。基準をクリアにすると、進捗管理や計画の振り返り・改善がしやすくなります。
人材育成の計画をたてる際には、個人のスキルマップを作成するのが一般的です。スキルマップとは、企業が求める人材のスキルごとに、社員の現状を評価するシートのこと。
これにより、社員一人ひとりが成長に取り組むべきスキルが可視化され、アプローチの解像度が上がります。できれば、スキルマップをもとに上司や同僚からの意見をもらいながら、自己評価や目標のすり合わせを行うとよいでしょう。客観的な視点を交えることで、より正確な課題意識をもち、高いモチベーションで取り組めるようになります。
取り組みの結果を評価する
人材育成研修において、一度立てた計画がそのまま順調に進み、期待通りの成果が得られるケースは珍しく、むしろほとんどの場合で改善点が残るものです。
取り組みを確実な成果につなげるためにも、結果を振り返り、評価しておきましょう。定期的な効果測定と改善により、PDCAサイクルを繰り返すことで、よりよい研修の仕組みを作り上げられるようになります。
まとめ
人材育成研修を考えるうえでのポイントや手法について解説しました。
「OJT」「Off-JT」「SD」に代表される基本的な手法と手順を押さえることで、自社に適した人材育成研修の仕組みが構築できます。
本記事で紹介したフレームワークを参考に、自社の成長に貢献できる人材育成研修を目指していきましょう。
パートナー企業