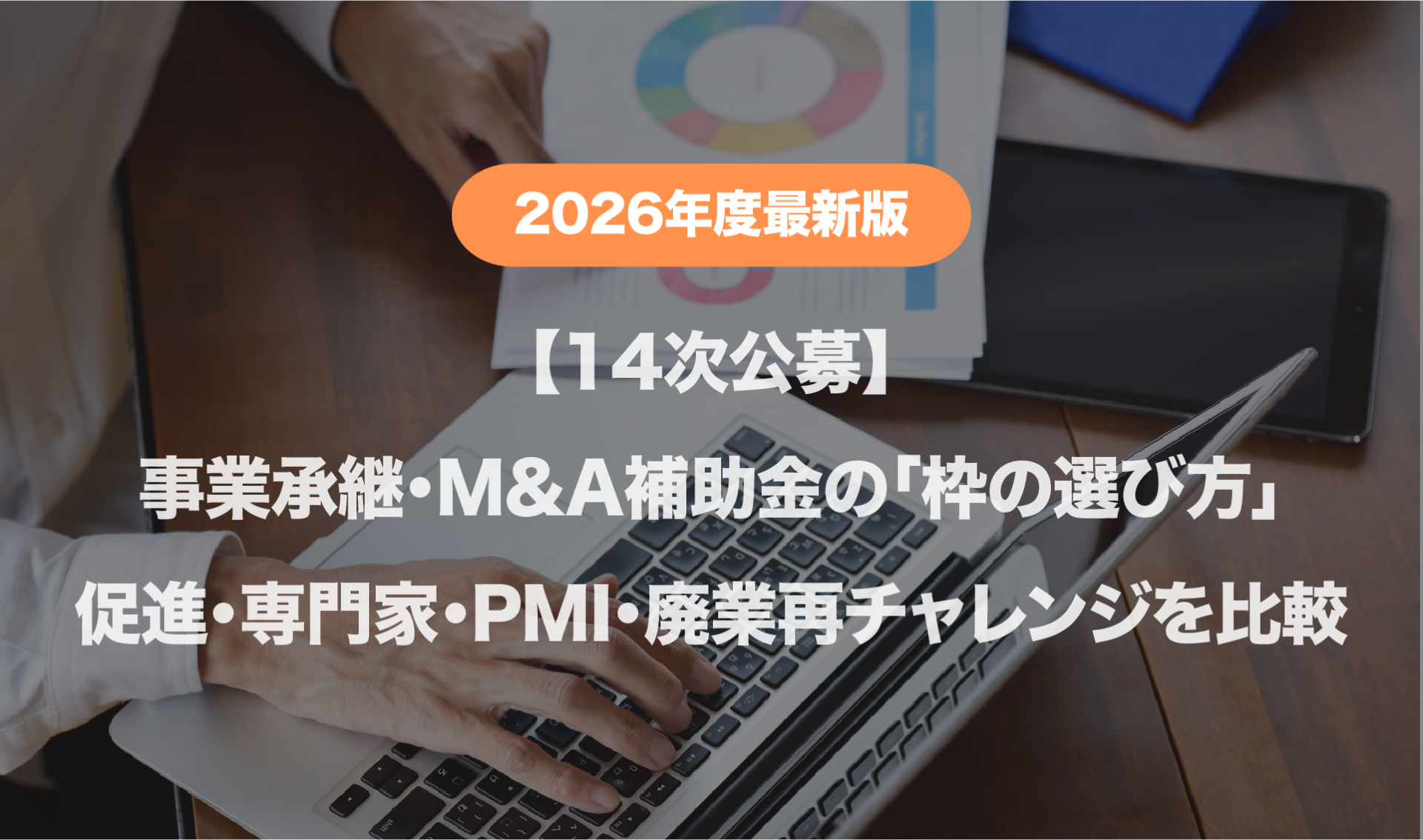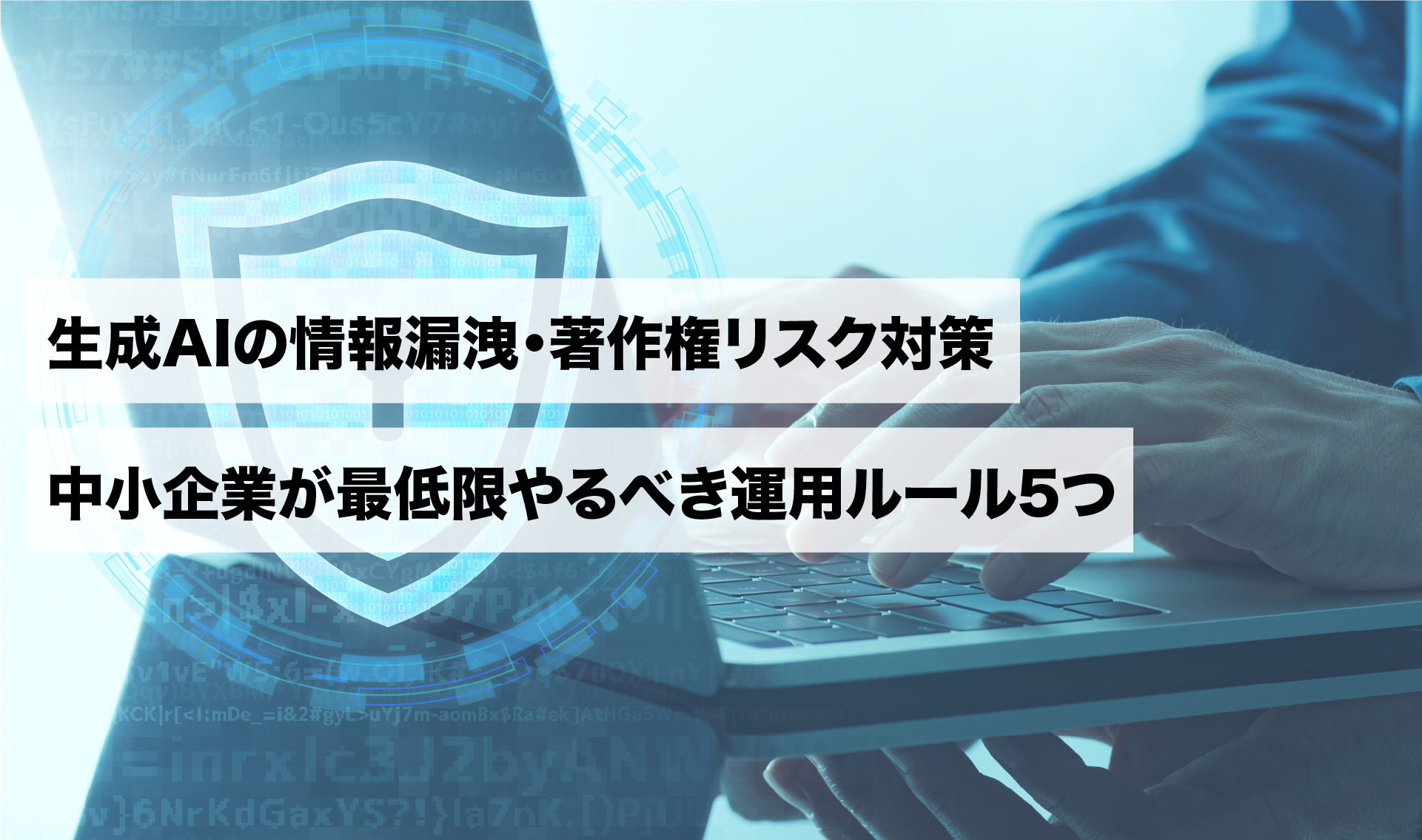DXの内製化とは?内製化のメリットとデメリット、企業事例を解説

自社のシステム開発や運用はこれまでアウトソーシングされる傾向にありましたが、求めるものが業務効率化から価値創出へと変化する中で、内製化に取り組む企業が増えています。今回はDXの内製化とはどういったものか、内製化のメリットおよびデメリット、そして企業事例をご紹介します。
目次
DXの内製化とは?
内製化とはこれまで社外に委託していた業務を社内で行うことです。「DXの内製化」とは、DX関連のシステム開発などを社内で行うことを指します。従来、ユーザー企業はITベンダー企業に大きく依存する傾向にありましたが、近年は内製化へのシフトが見られます。
ガートナージャパン株式会社は2023年1月、日本におけるソフトウェア開発の内製化に関する調査結果を発表しました。ユーザー企業でソフトウェア開発に従事する個人を対象に自社の内製化に対する見解を尋ねたところ、企業の方針が内製化の方向という回答は54.4%、外製化の方向という回答は35.4%という結果でした。
参考:Gartner、日本におけるソフトウェア開発の内製化に関する調査結果を発表
DXの内製化が必要な理由

DXの内製化がなぜ必要なのでしょうか。先述のガートナーの調査結果をもとに内製化の理由を考えてみます。
コストの最適化
ガートナーの調査で、自社の方向性が内製化であると回答した回答者が最も多く挙げた理由が「開発コストの削減」(複数選択可で全体の55.2%)です。ベンダー企業にシステム開発を外部委託する場合、アウトソーシング費用が発生します。ユーザー企業が、ベンダー企業による見積もり金額が適切かどうかを判断することは容易ではありません。特定の企業の製品やサービスを組み込んだ構成でシステム構築を行い、その製品やサービスに大きく依存してしまう「ベンダーロックイン(Vendor lock-in)」も懸念されます。ベンダーロックインの状態では、製品やサービスの値上げが起きても他社への切り替えは困難であり、コスト増大につながります。
柔軟で迅速な開発が求められる
ガートナーの調査で、内製化の理由として開発コスト削減に次いで挙げられた理由が「開発、実装、保守対応の迅速化」(同49.7%)でした。これまでのシステム開発では、ベンダーによるウォーターフォール型の開発が行われてきました。ウォーターフォール型は、要件定義、設計、実装、テストという流れで開発を進めます。開発工程が上流(要件定義)から下流(テスト)へと進行するため、ウォーターフォール(Waterfall:滝)型と呼ばれます。ウォーターフォール型は、最初に詳細な要件定義を行い、それに基づいて開発を進めます。開発途中での仕様変更は基本的に想定していません。このようにウォーターフォール型では、柔軟な開発が困難です。ユーザー企業は、全機能の実装が終わり、テスト工程に入るまで機能の確認ができません。ユーザー企業の要件が満たされていない場合、開発の後戻りが発生し、開発期間が長期化します。
DXの内製化のメリット

DXの内製化によるメリットは、開発スキル・ノウハウの蓄積と開発期間の短縮です。
開発スキル・ノウハウの蓄積
ベンダー企業に開発を「丸投げ」する場合、ユーザー企業は自社内に開発人員を抱え込む必要はないという利点があります。しかし、開発を完全に外部委託してしまうと、社内に開発スキル・ノウハウが蓄積されません。自社の競争力向上を図るためには、社内にDXを牽引するDX人材の存在が不可欠です。ここでいうDX人材とは、自社のビジネスを深く理解した上でデジタル技術の活用にも精通した人材を指します。内製化によって社内の人材に開発経験を積ませようとすることは当然の流れといえるでしょう。
開発期間の短縮
近年、ウォーターフォール型に代わる開発手法としてアジャイル型が注目されています。アジャイル(Agile)は「素早い」「機敏な」といった意味があります。アジャイル型はイテレーション(Iteration)と呼ばれる短い開発期間のサイクルを定め、要件定義、設計、実装、テストを繰り返す開発手法です。ウォーターフォール型のような詳細な要件定義は行わず、スピードが求められる開発や頻繁な仕様変更が発生する開発に向いています。
米国ではアジャイル型が採用され、ユーザー企業主体で開発を行うケースがほとんどです。一方、日本ではユーザー企業がベンダー企業に開発をすべて委託するケースが多く見られます。日本のベンダー企業はアジャイル型を行う人材の不足などからアジャイル型を敬遠し、ウォーターフォール型を選択する傾向があります。DXの内製化をアジャイル型で行うことにより、開発期間の短縮を実現できます。
DXの内製化のデメリット

DXの内製化はメリットだけでなく、DX人材の不足やコスト意識の希薄化というデメリットがあります。
DX人材の育成に時間がかかる
システムの内製化を始めようと思っても、自社のビジネスとデジタル技術の双方を熟知したDX人材が社内におらず、内製化に踏み切れないケースもあるでしょう。すべての企業にとってDX人材の採用・育成は頭の痛い問題です。自社に合った人材が簡単に見つかるとは限りません。人材を採用しても戦力になるまでに時間を要するケースも少なくありません。優秀な人材が自社にとどまらず、他社に流出してしまう可能性も考えられます。
コスト意識の希薄化
開発を外部委託する場合、何に対してどれくらいのコストがかかっているのかを把握し、できるだけコストを抑えようとする意識が働きます。しかし、内製化の場合は社内に人材を抱えているため、コスト意識が希薄になりがちです。人材が十分に育っておらず、スキルが低い場合、開発期間が長期化してコストがかさむ可能性があります。
DX内製化の進め方

DXの内製化を進める方法として、ノーコード開発の導入とベンダー企業との共創が挙げられます。
ノーコード開発の導入
ノーコード開発とは、コーディング(コードを書くこと)をせずにWebサイトやアプリの開発を行うことです。開発を行う際のハードルの1つはコーディングではないでしょうか。プログラミング言語の文法が分からないので開発に取り組めないという方も少なくないでしょう。ノーコード開発は、大規模な開発には不向きですが、小規模なツールの開発などであれば、マウスによるドラッグアンドドロップを中心とした操作で開発可能です。非ITエンジニアであっても、開発ツールの使い方を学べばWebサイトやアプリを開発できます。
内製化を支援するベンダー企業とパートナーシップを結ぶ
ユーザー企業にとってベンダー企業への依存は改善すべき点ではありますが、システムの開発力という点ではベンダー企業に一日の長があります。ユーザー企業がDXの内製化を進めるための現実的な解決策としては、ベンダー企業のサポートを受けながら内製化を一歩ずつ進めることが挙げられます。経済産業省が2020年12月にリリースした「DXレポート2」には、ベンダー企業の目指すべき方向性に関して、「ユーザー企業とDXを一体的に推進する共創的パートナーとなっていくことが求められる」と記載されています。
DX内製化の企業事例

星野リゾートとビックカメラの内製化の事例をご紹介します。
株式会社星野リゾート
全国にリゾートホテルや温泉旅館を展開する星野リゾートは、「DXは目的を達成するための手段」としてとらえ、現場主導でDXを推し進めてきました。従来は外部パートナーとともに自社独自のシステム開発を行ってきましたが、改善のスピードを高めるために内製化に踏み切りました。同社には、ノーコードツールによるアプリ開発を行うチームが存在します。チーム全体でアプリによる社内の課題解決に取り組んでおり、現場スタッフのアナログでのシフト管理も、アプリでデジタル管理できるようにしました。
株式会社ビックカメラ
大手家電量販店のビックカメラは、社内エンジニアによるシステムの内製化に取り組んでいます。2022年9月にはグループのDXを推進する「株式会社ビックデジタルファーム」を設立しました。エンジニアを直接雇用したほうがITベンダー経由で確保するよりもコストダウンを図れるというメリットもありますが、最大のメリットは「スピーディーな顧客体験の変革」であると言います。クラウドの活用に積極的であり、システム内製化に「Salesforce Lightning Platform」「アマゾン ウェブ サービス(AWS)」をプラットフォームとして採用しています。
まとめ
今回はDXの内製化についてご紹介しました。各企業ともITベンダー依存から脱却し、自らのシステムを自らの手で作っていくという内製化の流れが顕著になっています。内製化できる部分と外部委託する部分を明確にし、少しずつ内製化を進めてみてはいかがでしょうか。
パートナー企業