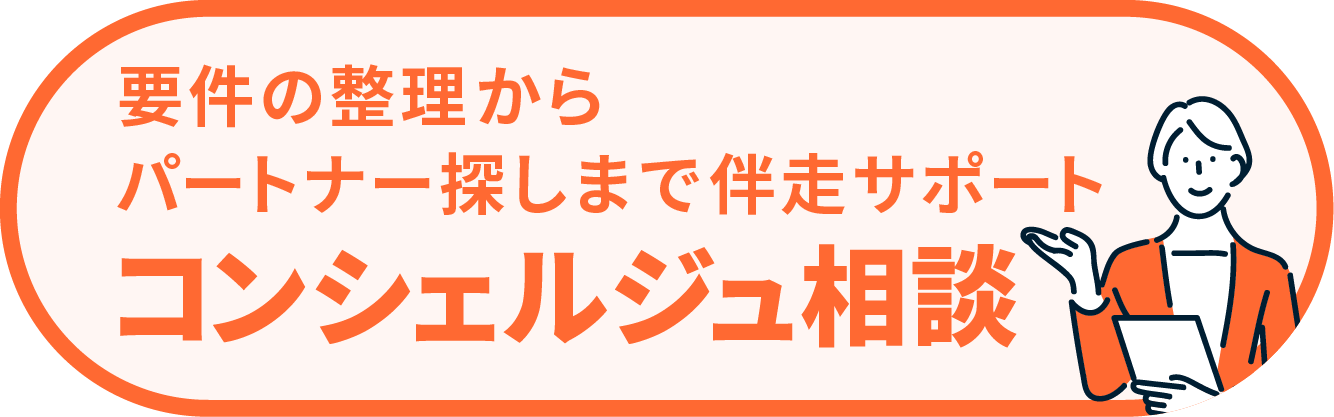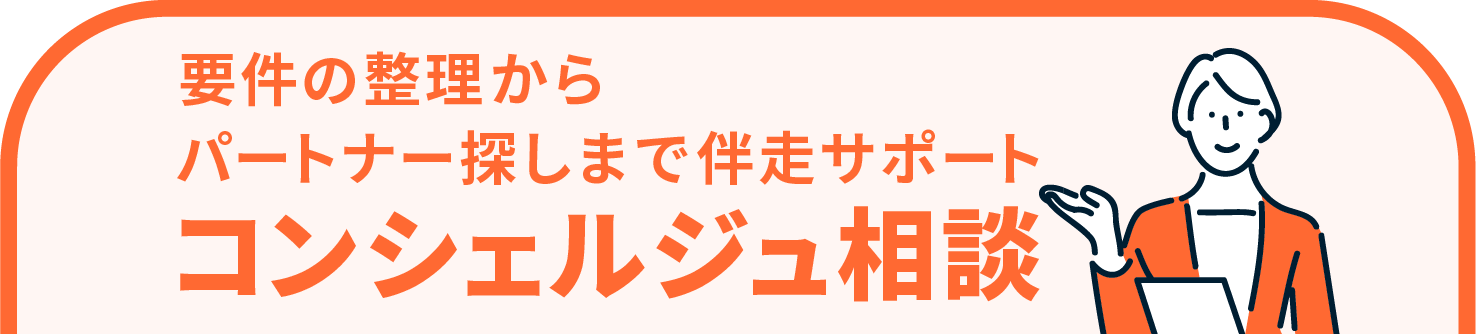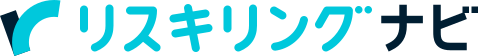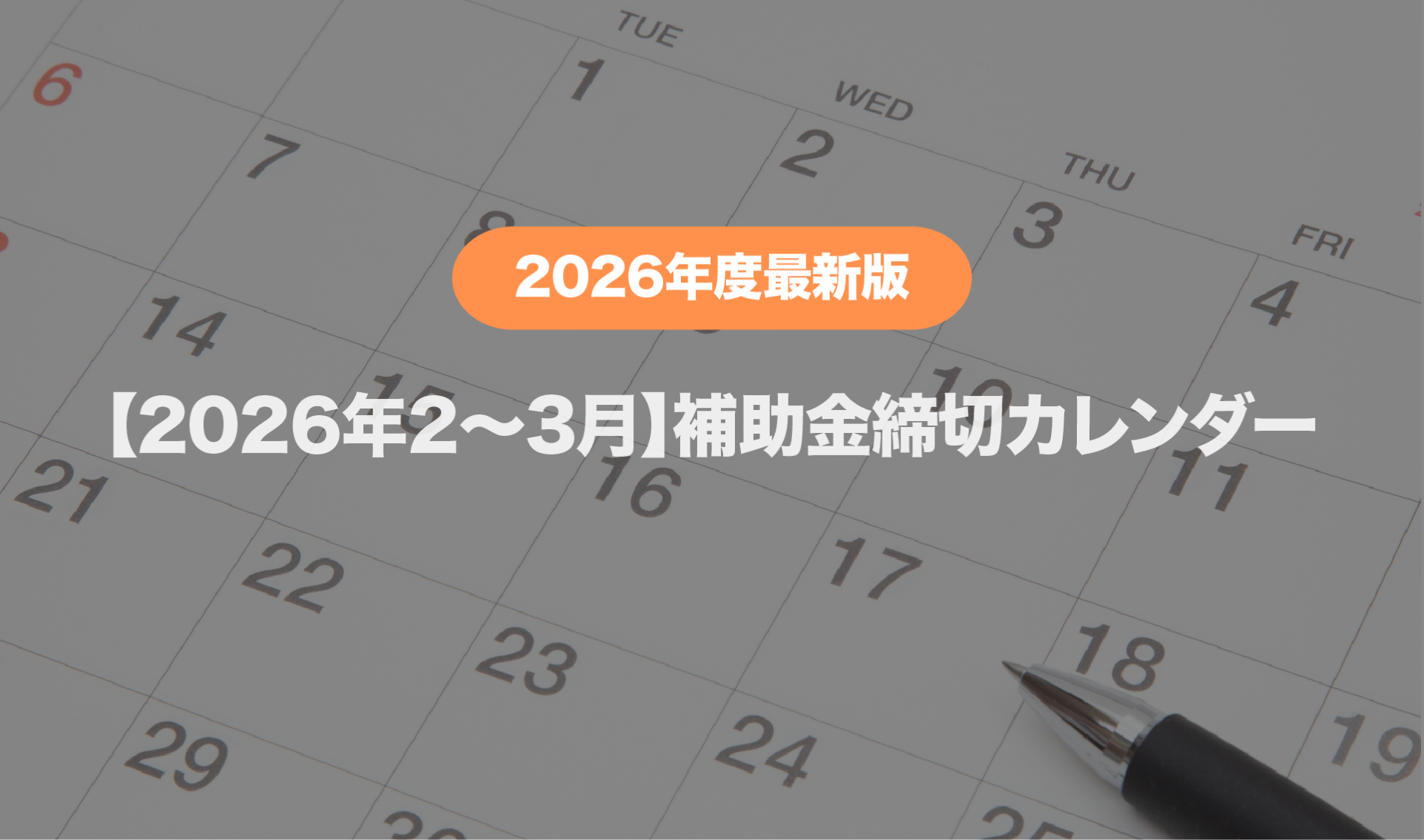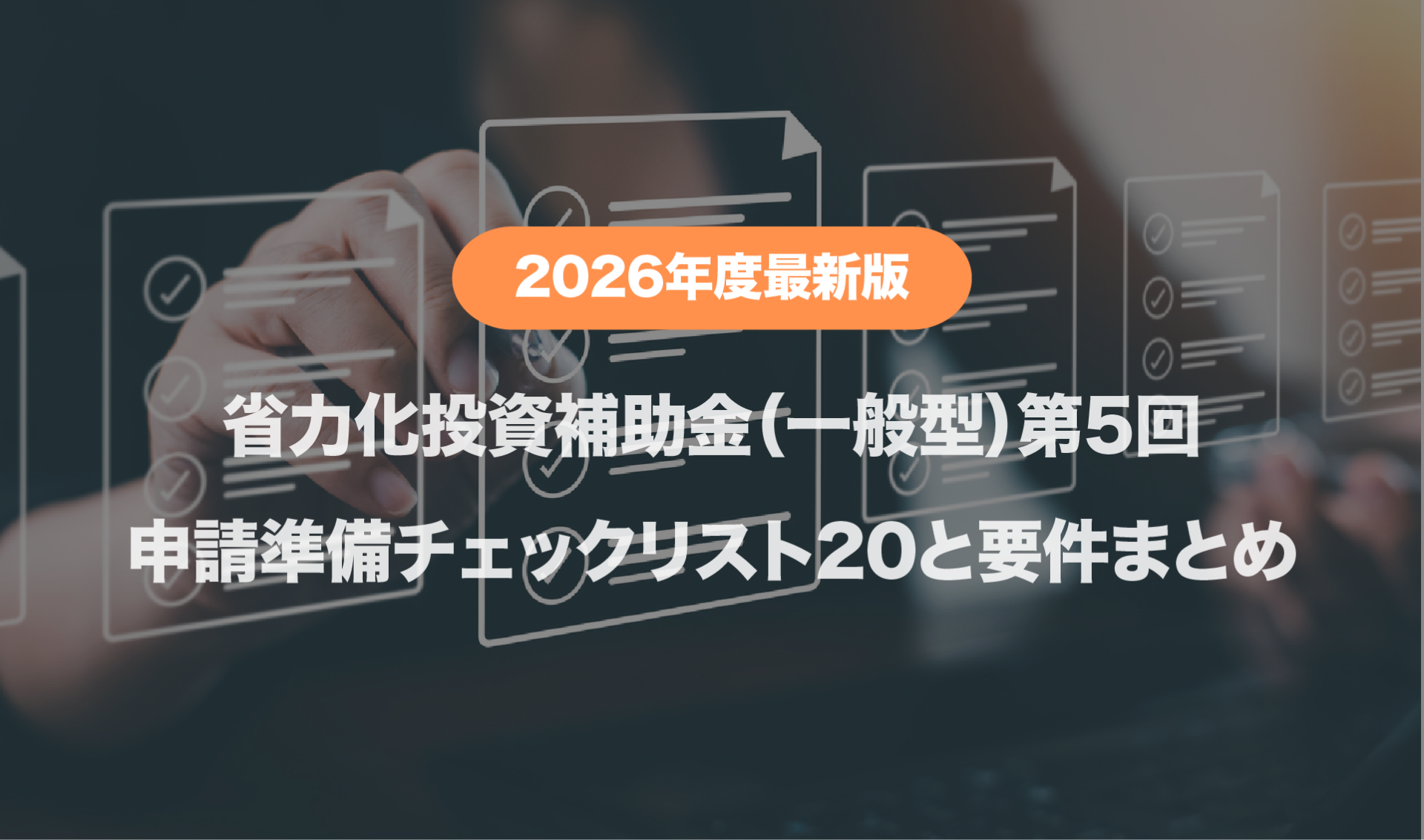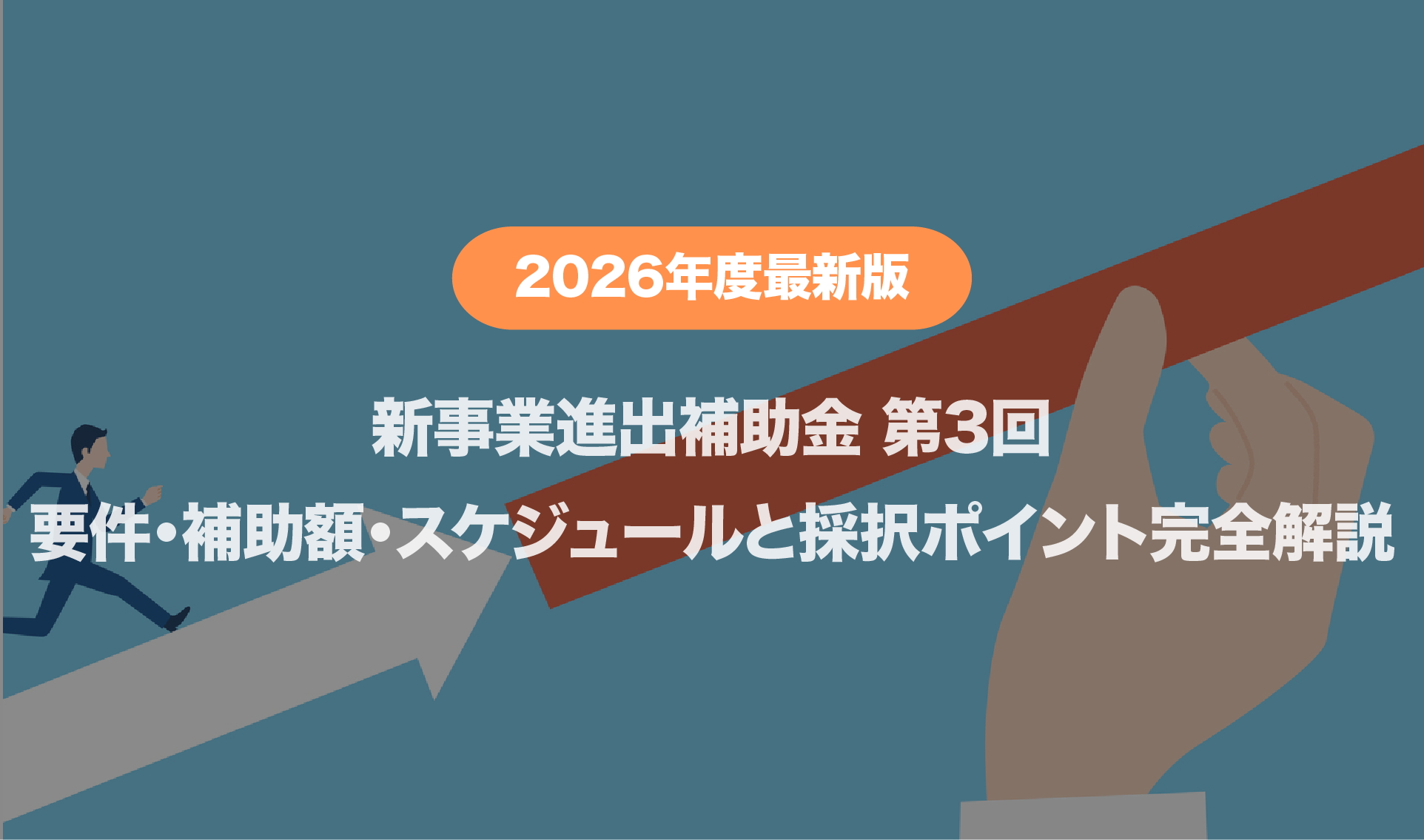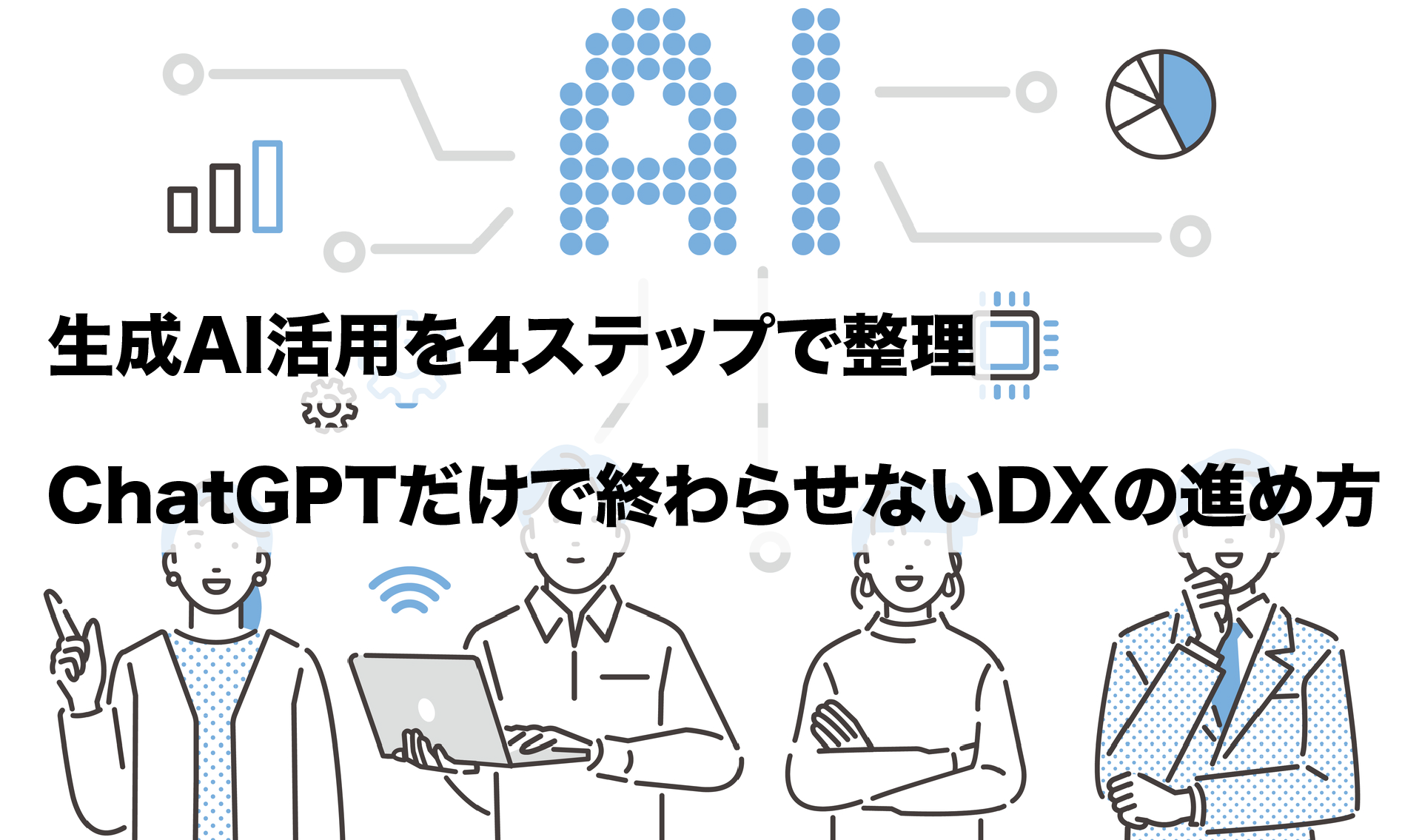【2025年度】専門家費用を国が支援!事業承継・M&A補助金「専門家活用枠」の基礎知識と申請時の注意点について
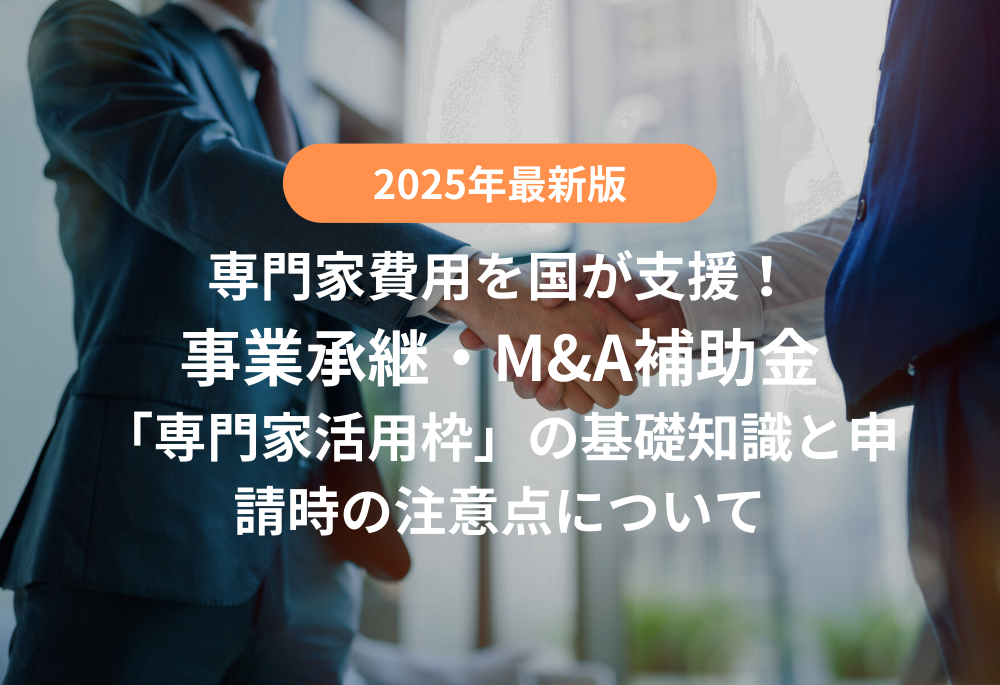
中小企業が事業承継やM&Aを進める際、法務や税務、財務など多岐にわたる専門分野の知見が必要となり、外部の専門家を活用するケースが増えています。しかし、その費用は決して安くなく、実行をためらう要因にもなり得ます。こうした課題を解消するために、国は「専門家活用枠」という補助金制度を設け、中小企業の円滑な承継・再編を支援しています。本記事では、この制度の仕組みや活用するメリットについて詳しくご紹介します。
目次
事業承継・M&A補助金「専門家活用枠」とは?
補助金制度の概要と目的
中小企業が事業承継やM&A(企業統合や事業再編を含む)を実施する際に必要となる、専門家(M&Aアドバイザーや士業など)の支援費用を軽減することを目的としています。
専門的な知見が求められる事業承継・M&Aの過程では、外部の力を借りることが成功の鍵となりますが、費用負担が大きな障壁になることも少なくありません。こうした課題を補助金によって和らげることで、中小企業が円滑に事業を次世代へと引き継ぐことを後押しします。
その結果、後継者不足による廃業リスクの軽減や、地域経済の活力維持、さらには雇用の確保につながり、日本全体の経済基盤の安定にも寄与することが期待されています。
どのような企業が対象になるのか?
事業承継・M&A補助金「専門家活用枠」の対象となるのは、主に中小企業基本法に基づく中小企業者です。製造業、小売業、サービス業など、業種は幅広く、地域性も問いません。具体的には、親族内承継、第三者承継(M&A)、役員・従業員への引継ぎなど、一定の承継形態に該当すれば対象となります。
▼対象となる中小企業者・小規模企業者
| 業種 | 資本金または出資金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業など | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
※これより小規模な事業者(いわゆる「小規模企業者」)も対象に含まれます。
補助対象となるのは、日本国内に拠点や居住地を持ち、国内で事業を営んでいる中小企業者です。申請にあたっては、M&A支援機関に登録されているFAや仲介業者が、申請者本人(または法人代表者)と同一人物でないことも条件となります。
また、過去18か月以内に中小企業庁の補助金で賃上げ加点の要件を満たしていなかった場合、正当な理由がない限り、大幅な減点対象となります。
支援類型ごとの要件を正しく理解しましょう
「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)」では、補助対象者の目的や立場に応じて、支援が2つの類型に分かれています。それが「買い手支援類型」と「売り手支援類型」です。どちらに該当するかによって、求められる要件や実施すべき取り組み内容も異なります。
この制度を正しく活用するには、それぞれの類型がどのような条件を満たす必要があるのか、あらかじめ把握しておくことが重要です。以下では、買い手支援類型と売り手支援類型、それぞれの要件について詳しく解説します。
▼買い手支援類型における要件
買い手支援類型として補助を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
・事業再編や事業統合によって他社から経営資源(人材、設備、取引先など)を譲り受けた後、それらを活かし、生産性向上や業務効率化などの効果が見込まれること。
・同様に、経営資源を引き継いだ後に、地域の雇用維持・創出などを通じて、地域経済全体に好影響を与えるような事業を行うことが期待されていること。
・M&Aの実行にあたっては、客観的な資料に基づく十分な検討を行い、契約後のトラブルを防ぐとともに、M&A後の成長を実現するために重要となるPMI(統合プロセス)を意識した取り組みとして、デュー・ディリジェンス(DD)を実施することが求められます(補助対象経費に含まれていなくても実施は必須です)。
▼売り手支援類型における要件
売り手支援類型の場合は、以下の要件を満たすことが必要です。
・地域経済を牽引するような事業を行っており、雇用の確保や地域への波及効果が期待される企業であること。そのうえで、事業再編や事業統合を通じて、第三者による事業継続が見込まれることが求められます。
補助金の対象となる主な経費項目
補助対象経費とは、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、①〜③のすべての要件を満たし、なおかつ事務局が必要かつ適切と認めたものを指します。
① 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものであり、明確に特定できる経費
② 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
③ 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費
補助対象経費の概要は、以下のとおりです。
| 類型 | 補助対象経費の区分 |
|---|---|
|
買い手支援類型 (Ⅰ型) 売り手支援類型 (Ⅱ型) |
|
補助対象経費とは、事業の遂行に必要であり、期間内に契約・支払いを行い、証拠書類で確認できる経費のうち、事務局が適切と認めたものです。買い手支援類型・売り手支援類型のいずれにおいても、謝金や委託費、移転費用など幅広い経費が補助の対象となります。
補助率と上限額について
補助対象者に交付される補助金額は、補助対象経費の3分の2以内とされており、上限額などは以下のとおり定められています。
| 類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 | 上乗せ額 (デュー・ディリジェンスに係る費用) |
上乗せ額 (廃業費) |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い手支援類型(Ⅰ型) | 補助対象経費の2/3以内 | 50万円 | 600万円以内 | +200万円以内 | +150万円以内 |
| 売り手支援類型(Ⅱ型) | 補助対象経費の1/2または2/3以内 | 50万円 | 600万円以内 | +200万円以内 | +150万円以内 |
※注1:申請時の補助額が補助下限額(補助対象経費に2/3または1/2をかけた金額が50万円)を下回る場合は申請できません。
※注2:売り手支援類型において、所定の要件を満たす場合は補助率2/3以内、該当しない場合は1/2以内となります。
補助金は、補助対象経費の3分の2以内を上限として交付されます。買い手・売り手支援類型ごとに補助率や上限額、上乗せ額が定められており、最低補助額は50万円、上限は600万円以内です。さらに、デュー・ディリジェンス費用や廃業費に対して加算が認められる場合もあります。なお、売り手支援類型は条件により補助率が異なります。詳細は、必ず最新の公募要領をご確認ください。

事業承継・M&A補助金の公募はいつ?最新スケジュールを確認
2025年3月31日に、事業承継・M&A補助金(第11次公募)の暫定版公募要領が公開されました。確定版は2025年4月中に公表される予定で、今回の公募は「専門家活用枠」のみが対象となります。なお、申請スケジュールの詳細については、確定版の公募要領で正式に発表されますので、今しばらくお待ちください。
申請時の注意点|事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)
補助金を確実に受け取るためには、申請前からいくつかの重要なポイントに注意する必要があります。以下の点を押さえておくことで、申請の不備や不採択のリスクを避けることができます。
交付決定前の契約・支払いは対象外
補助金の対象となる経費は、「交付決定通知」が発行された後に契約・発注・支払いを行ったものに限られます。交付決定前に業務を開始すると、その費用は補助の対象外となりますので、着手のタイミングには十分注意してください。
申請内容の整合性・実現性が重視される
申請書には、具体的で実現可能なM&Aまたは事業承継の計画を記載する必要があります。事業の将来性や地域経済への貢献も審査対象となるため、内容が曖昧な場合は不採択となる可能性があります。
過去の補助金実績による減点
過去18か月以内に中小企業庁所管の補助金において、賃上げ加点の要件を満たしていない場合、正当な理由がなければ減点対象となります。過去の申請実績も確認しておきましょう。
登録支援機関との関係性にも要注意
M&A支援機関(FA・仲介業者)と申請者(または法人の代表者)が同一人物である場合、補助対象外となります。第三者性が担保されていることが求められます。
まとめ|補助金制度を上手に活用し、事業の未来を守ろう
事業承継やM&Aは、中小企業にとって避けて通れない重要な経営課題です。しかし、実際には「手続きが煩雑そう」「専門家費用が高いのでは?」といった不安から、一歩を踏み出せない経営者も少なくありません。そんなときこそ活用したいのが、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)」です。
この補助金制度を使えば、M&Aアドバイザーや弁護士、公認会計士などの専門家費用の一部が支援され、安心して事業承継を進めることが可能になります。また、適切な専門家の力を借りることで、後継者不在や廃業リスクといった問題の解消にもつながります。
補助金はタイミングと準備がカギを握ります。制度の詳細を把握し、必要な手続きを計画的に進めることが、将来の経営安定や成長への第一歩です。次世代に事業をつなぐためにも、早めに行動を起こしましょう。
パートナー企業