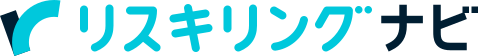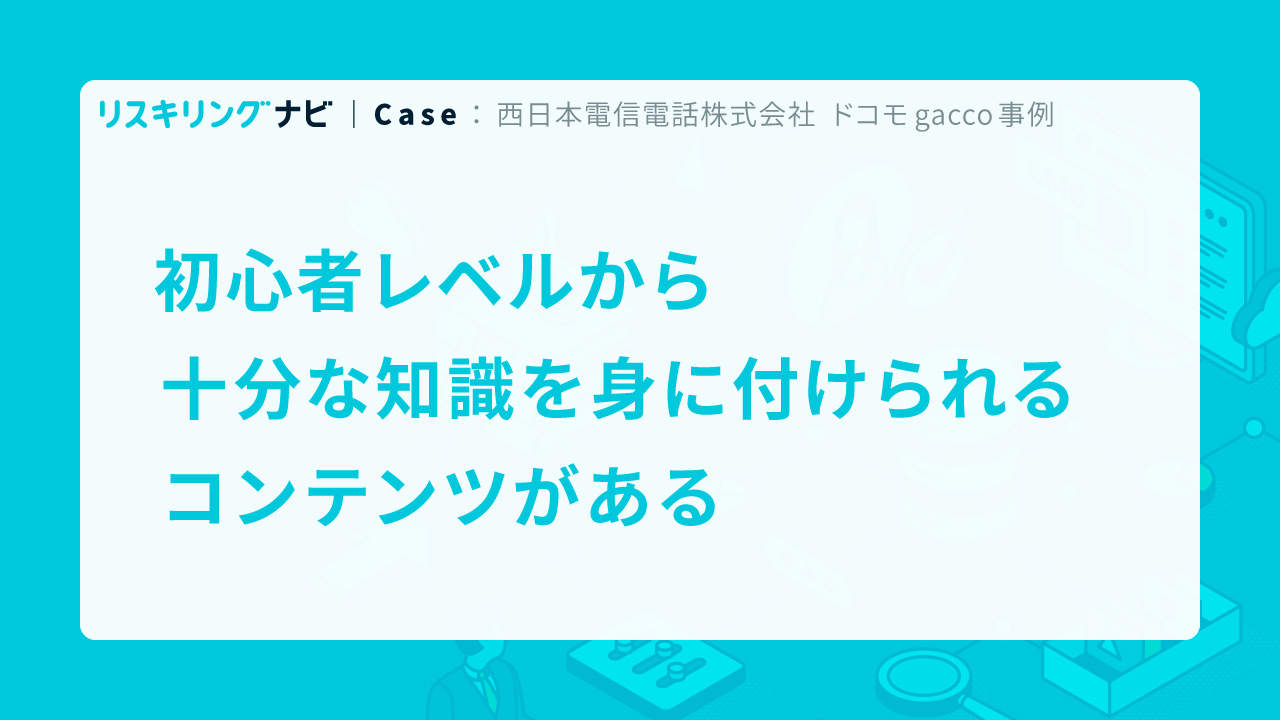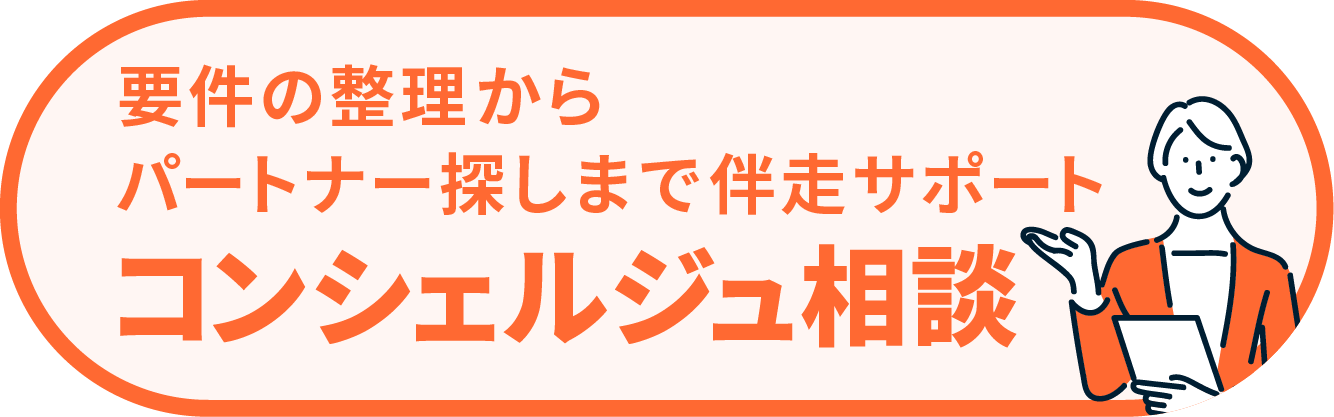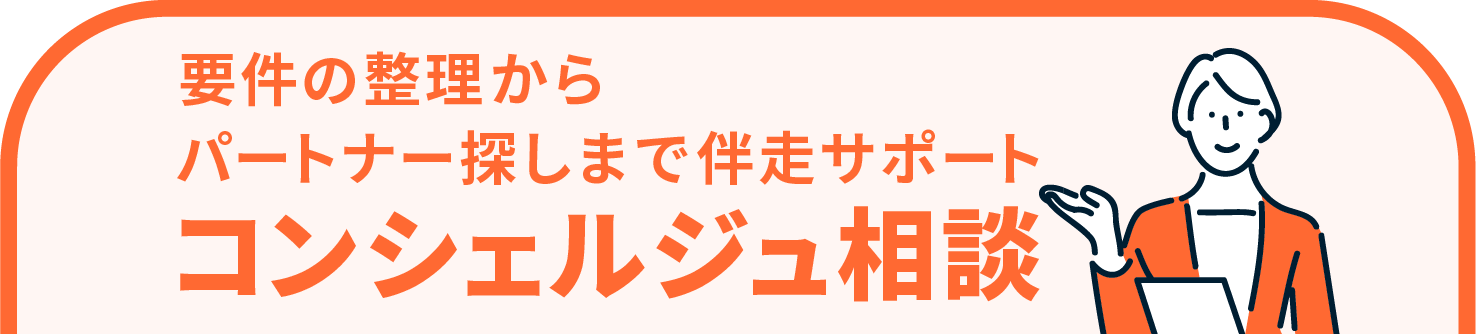目次
gaccoの導入前に抱いていた課題感を教えてください。
2020年頃、事業を支える根幹は「人」であるとの考えのもと、社員一人ひとりが高い専門性や能力を発揮し、事業を通じて高い付加価値を提供できる人材育成を進める方針を確立しました。特に注力したいと考えたのが、デジタル人材の育成です。デジタルデータの活用は生産性を向上し、利益を創出するために不可欠な要素だからです。しかし、全社員に対して初歩的なレベルから動機付けでき、実践で落とし込めそうなレベルの知識まで身に付けられるコンテンツは、なかなか見つかりませんでした。
これまでの人材育成の体制や制度について教えてください。
NTTグループのNTTラーニングシステムズが提供する講座を受講する形式です。研修の体制は、リアルの集合研修から通信教育までさまざま。年次などに応じて必ず受講する講座から、社員の興味関心のもとで受講するものまで、さまざまな講座を提供しています。
また、社員が外部のeラーニングを受けたり、資格取得に向けて受験したりする場合は、費用を負担しています。
導入した決め手を教えてください。
NTTラーニングシステムズから、デジタル人材育成に関するgaccoの有料コンテンツを紹介していただきました。まずは自分自身が受けてみたところ、初心者にも分かりやすく、徐々にレベルアップできることに魅力を感じました。
また当社では、人材育成の一つの目標として、社員が自律的に自分が必要なことを選んで勉強していく自学自習を掲げています。gaccoを導入すれば無料講座も含め、より幅広い学びを提供できます。自学自習する習慣にもつながると考え、導入を決めました。
導入後、どのような効果が得られましたか。
2020年に開始し、現段階で95%以上の社員が受講しています。アンケートでは、一番内容が難解だった統計学でも「よく理解できた」と答える人が5割。フリーのコメント欄でも、「業務で使えそうなヒントがあった」などのポジティブなコメントが多く寄せられました。特に若い世代がポジティブに受け入れている傾向がありました。また退職間際の方でも「第二の人生に使えそう」などの好意的な声がありました。
NTT西日本では、独自の認定制度を設けていると聞きました。
外部の認定制度では自社で必要なスキルを評価するのは難しく、データサイエンティスト協会の認定をもとに、独自にデジタル人材認定を始めました。B、A、SAの3段階で設けており、B認定はgaccoの講座を完了すること、A認定は外部資格を取得しているほか、データ活用して業務をした実戦経験を書く書類審査を通過すること、SA認定はその領域でデータ活用を推進できるかが面談で認められることで付与されます。現在、A認定は4022認定、SA認定は56認定と、着実にデジタル人材育成が進んでいます。
中にはA認定を取得したいけれども、業務の中で実戦経験が得られていないという声も聞きます。知識が十分に身に付いていても、実践でつまずいてしまうことは多々あると思いますし、人事部としても、いかに実践で成功経験を積めるかが、デジタル人材になる上で不可欠だと考えます。そこで、経験が不足している方には実践経験が積めるような部署にダブルワーク制度等を活用して参画できる機会を設けています。いずれは実戦経験をもった人たちが各部署に増えて、それを見て別の人が実践するサイクルを生み出していきたいです。
人材育成に関する今後の展望を教えてください。
社内では今、データサイエンティストのほかにも、セキュリティなど、さまざまな領域でスペシャリストを育成したいと考えています。
そのためには、gaccoをはじめさまざまな方法で専門的分野を学べる研修を体系付けていきます。認定制度についても、現時点のA認定は書類審査で付与しているため、真の実践力が身に付いていない可能性もあります。真の実践力を把握できるようなしくみづくりを進めていきたいですね。また、データサイエンス以外のスキルについても、実践力を一覧として見られるようなマトリックスを作成していきたいと考えています。
ほかにも現在の課題として、管理者層にデータサイエンスの講座の価値がうまく届けられていないことがあります。仕事の仕方に先入観を抱いているため、「このスキルは本当に必要なのか」と、新しい学びに消極的になっているのです。上司が変わらなければ、部下も変わりません。管理者層向けの研修を実施したりなど、より幅広い社員に刺さる人材育成を提供していきたいです。
ドコモgaccoのDX人材育成プログラムは、経済産業省が定める「デジタルスキル標準」に基づいた体系的なカリキュラムの提供により、 DX人材育成のスタートにお悩みの皆様の課題を解決できます。
詳細を見る